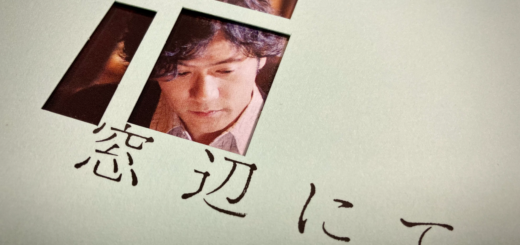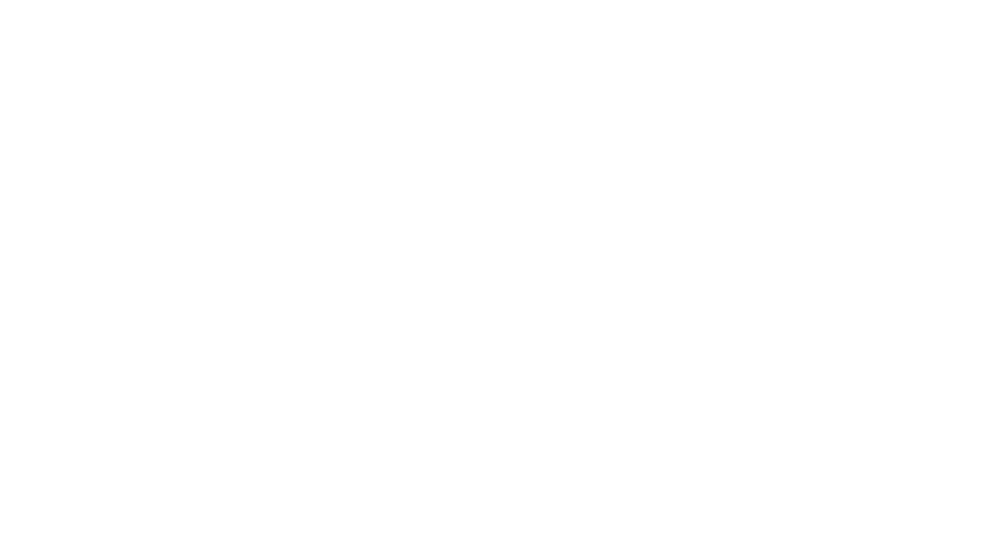『Mad Men』で考える、幸せとは何か。

遅れてきた極私的『Mad Men』祭り
2020年に観たベストな作品は何か? 餓鬼が喜ぶ鬼退治の話、なわけもなく、歌舞伎まがいの銀行ドラマにも食指は動かなかった。コロナ禍で個人の密かな楽しみとしていたのが『Mad Men(マッド・メン)』。2007年から2015年までアメリカで放映されたテレビドラマだった。
1960年代、ニューヨークの華やかな広告業界を舞台としたストーリーで、広告代理店の多くが本拠を置くMadison AvenueからMad Men。仕事中の飲酒に喫煙、セクハラにパワハラ、人種差別に同性愛差別と、21世紀の社会通念とは相容れない当時の風俗が赤裸々に再現されており、政治的配慮からオブラートに包まれた、ぼやけた表現に慣れてしまった現代人には、良くも悪くも刺激的である。
主人公ドン・ドレイパーは、アドエージェンシーの敏腕クリエイティブ・ディレクター。業界内で名声を博し、自信満々で辣腕をふるう彼にはひた隠しにする暗い過去があり、不幸な生い立ちと、他人に成り代わって生きているという嘘に、たえず苦しむことになる。美しい妻と子供たちに囲まれながら、家族への愛情というもの感じることができず、容姿端麗も手伝って、女遊びがたえない。
そんなドンと個性的な仕事仲間や家族たちが、エスタブリッシュメントの街ニューヨークで夢を見、傷ついては何度でも立ち直ろうとする群像劇は、3ヶ月1クールから抜け出せず、せせこましいばかりの日本のドラマと違い、ひとり一人のキャラクターがしっかりと表現されていて、まるでそれぞれが実在するかのようなリアリティを勝ち取っている。
冷蔵庫のなかの夢
全7シーズン、92話というドラマの最終話は、極めて印象的だった。
ドンは、これまで築いてきた富や名声、家族を捨て、逃避の旅に出る。行き着いた先は、ニューヨークからは地の果てにあたるアメリカ西海岸。娘から元妻の病気を知らされるも、その妻には「あなたの助けはいらぬ。このまま静かに最期を迎えさせてくれ」と自らを拒絶され、精神的にも物理的にもいよいよ行き詰まったドンは、ひょんなことから参加することになった自己啓発セミナーで、ある男の告白を聞く。
彼の名はレナード。他の参加者と違って複雑な問題は抱えておらず、「つまらない男」と自分を呼ぶ彼は、どこにでもいる普通の中年男に見え、ごく普通にオフィスで働き、妻も子もいる。しかし、幸せであるという感覚とは無縁に生きてきた。
自分は誰にも見られていない。
自分が消えても誰も気にしない。
みんなに愛されているはずなんだが、それが何か分からない。
“誰も与えてくれない”と、ずっと思い続けている。
いや、与えようとしてくれたことは分かっているけど、それが何か分からない。
こうした独白に、茫然自失だったドンは、やがて何かに気がついたように、彼に視線を向けはじめる。
そして、レナードの見た夢の話は、ドンの心をわし掴みにする。
冷蔵庫の棚に自分が座っている。
扉が閉まって、明かりが消える。
外ではみんなが食事をしている。
扉が開いて、みんなが笑っている。
私を見て喜んでいる。
でも、本当は見ていない。
私を選びもしない。
また扉が閉まって、明かりが消える。
そう言い終えて泣き崩れるレナードに、ドンがゆっくりと歩み寄り、きつく抱きしめる。
レナードとドンが共有した苦しみの正体は、他の誰かではなく、自分の心のなかの問題だ。
2人ともごく普通の生活を送り、恵まれているように見える。
すべてを持ち合わせているように見える。
でも、「心のなかにあるべき何かがない」という欠落の意識が、彼らを幸福感から遠ざけてしまう。
ここで示されるのは、結局、ひとは他人とではなく、自分自身と折り合いをつけないと幸せにはなれないということ。自分を受け入れ、愛せないひとは、他人も愛せない、ということ。そしてそんな自分の内なる問題は、レナードのような他人の力を借りてこそ、克服できるということだった。
明と暗、画作りの妙
ストーリーのおもしろさもさることながら、このドラマの画作りには感心させられることが多々あった。特にシーズン5最終話の最後の3分間には脱帽するばかりであった。
ドンは、2人目の妻である女優志望のメーガンに、自らが担当する広告クライアントのCMオーディションに出させてほしいとせがまれる。最初は乗り気じゃなかったドンだったが、結局、若妻の望みをかなえてしまう。
スタジオでスポットライトを浴び、おとぎ話の中にいるような夢見心地のメーガンを、暗がりから見つめ、その場を立ち去るドン。この明と暗は、ふたりの行く末を暗示するかのようであり、またドン自身の表と、腹の底の複雑な感情をあらわしているかのようである。
流れる曲は、映画『007は2度死ぬ』から、ナンシー・シナトラの『You Only Live Twice』と、ここにもプリセットされる“2つの人生”。日本で撮影された007作品のオマージュか、ドンが訪れたバーはどこかエキゾチックですらある。酒を注文するとき以外一言も発さないドンの心境は、彼の表情と置かれた場所、そして逆ナンしてきた若い美女を見る流し目をヒントに推しはかる。言葉がなくとも、十分に雄弁なシーンだった。
描かれる広告の“功と罪”
ドン・ドレイパーの華麗なる人生と内なる孤独という2つの“顔”と並走するテーマが、広告の“功と罪”だった。ドラマのなかでは、広告に関するネガティブかつシニカルな意見が散見される。いわく、ひとを騙して物を買わせる。いわく、大量消費社会の片棒を担ぐペテンである。こうした押し売り的な広告の側面に対し、いや、広告もまんざらではないんだ、と思わせるエンディングが用意されていた。
92話目、最終話の最後では、レナードとの邂逅でどん底から這い上がる何かを掴んだドンが、瞑想にふけりながらアルカイックな微笑みを見せる。そして、コカ・コーラのCM「Hilltop」で、長い長い物語が幕を閉じる。このCMは、実際に1971年につくられ放映されたもので、マッキャンエリクソン社、つまりドラマの最後にドンが在籍した、実在のエージェンシーが手がけたものである。
のちにドンがつくったであろうことが暗示されているこの広告では、コカ・コーラを売らんとする商魂は希薄だ。描かれるのは、様々な人種が集い、ともにひとつの歌を歌うという理想の社会。コカ・コーラは、その理想の実現を助ける媒介物、ひとを結びつけるためのきっかけに過ぎない。
分断と混乱に揺れたアメリカの1960年代は終わった。次の時代に、新たな希望を持って進もうではないか、という力強いメッセージが込められたCMは、ドンにとっても、そのドンが生きた広告業界にとっても、救いに満ちたエンディングとして相応しいものだった。■bg