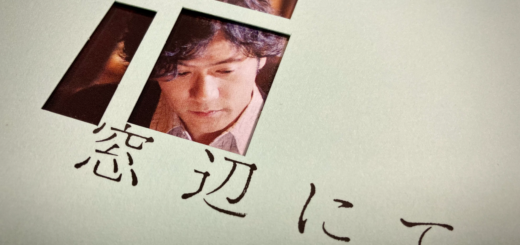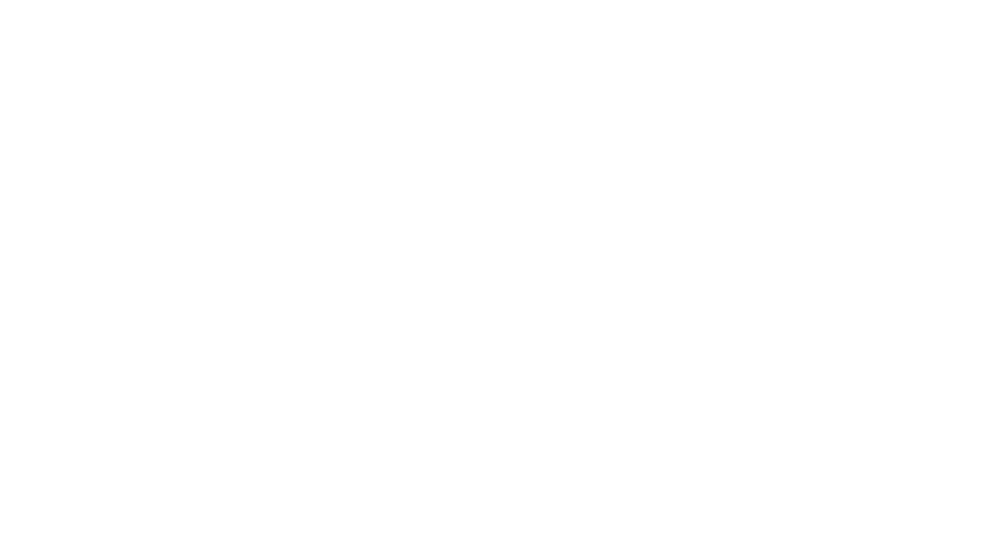賛否両論のドラマ『いちばんすきな花』の何が今日的なのか

4人の主人公を中心とした「生きづらさを感じるひとたち」のストーリー
2023年秋に注目を集めたフジテレビのドラマ『いちばんすきな花』。「男女の間に、友情は成立しますか?」という、いささか凡庸なコピーが踊る本作は、実に繊細で、極めて今日的なテーマを内包していた。
このドラマでは、全編を通じて、主人公の4人の男女を中心とした「生きづらさを感じるひとたち」への慰めの言葉が次々と繰り出される。
その4人とは、「2人組を作るのが苦手だった」という潮ゆくえ(多部未華子)、「2人組にさせてもらえなかった」春木椿(松下洸平)、「1対1でひとと向き合うのが怖かった」深雪夜々(今田美桜)、そして「1対1で向き合ってくれるひとがいなかった」佐藤紅葉(神尾楓珠)。子供の頃から対人関係に悩んできた4人がふとしたきっかけで出会い、親交を深めていくストーリーだ。
リアルタイムでネット民の感想を追ってみたが、共感するひとと、全く理解できないひと、両極端な意見が散見された。それだけ好き嫌いが分かれた理由は、どこにあったのだろうか。
友情?恋愛?白とも黒ともつかない関係
『いちばんすきな花』の賛否が分かれた理由のひとつは、特段の事件もなく、起伏のない淡々とした話が続くこと。屈折した4人の主人公それぞれが放つ光が乱反射し、捉えどころのないエピソードが連続し、テーマがぼやっとしているのだ。
やがて志木美鳥(田中麗奈)というひとりの女性が、4人の共通の知人であるという奇跡的(かつ強引)な発覚を経て、発散した光も少しずつ収斂し始めるものの、最終的にどんなまとめ方をされるのか、最終回まで見当がつかなかった。
劇中、椿が住んでいた通称「椿ハウス」が物語を象徴するような場所となり、心の拠り所のなかった4人の文字通りのホームとなる。しかし、同じような悩みを抱える4人が肩を寄せ合うという構図だけなら、たんなる馴れ合い話になってしまう。これで満足などされるはずもない。
また、主人公同士で恋愛の要素がないわけでもないが、白とも黒ともつかない微妙な関係に終始する。「男女の間の友情」と言われても、それがいったいどんなものかも、フワッとしすぎていて想像がつかない。
従来までの“ドラマの型”にハマらず、何によって登場人物が(良き方向へ)変わっていくのか、いっこうに掴めないのだ。
価値を特定せず、無理に押しつけない
このドラマが刺さるひとには、何が刺さったのか。“構図”や“型”という大雑把な括りではなく、セリフのひとつひとつ、あるいはストーリーの組み立て方にある「伏線と回収」という細かな妙に熱狂する向きが、非常に多かったのではないかと思う。
登場人物はみな繊細で優しく、誰もがなるべく敵をつくらないようにしている。恋愛だなんだと価値を特定せず、無理に押しつけない。はっきりとした分かりやすい大義名分がないぶん、全方位的ではなく、局面やキャラクターごとに、狭い層に局所的にメッセージが届く。逆にそうした機微を受容できないと、何の話だか理解しづらい。
昭和の御代には、「トレンディ・ドラマ」という、“誰もが憧れるとされた恋愛やライフスタイル”という泡沫の夢を見させられたものだった。価値は単一で、勢いはあったが、今思えば大雑把で大味だった。
平成、令和と時代の変遷を目撃してきた筆者からすれば、『いちばんすきな花』に見られる細やかさは、実に今っぽいと感じられた。
正論が支配する世界の副作用
それにしても、主人公らが抱える自己拘束感の強さ、自意識過剰さには少々心配になった。「それ、気にしすぎじゃないの?」と思わなくもないが、かといって「気にするな」と言われ気にしなくなれば誰も苦労はしない。
実際、我々が気にしなければならない事柄は増えるばかりだ。
SDGsにコンプライアンス、あるいは#metoo、反社や喫煙の一掃、SNSを通じた自由な発信など、ある種の正論が正論として堂々と主張できる世のなかになったことには良いところもある。
しかし、人間が清らかで真っ直ぐな、矛盾のない存在になれない以上、正論が支配する世界には副作用としての軋みが生じる。生きづらさを、個人の生い立ちや性分のせいだけにはできない。強い拘束と硬直を強いてくるのは、むしろ社会の方である。
本作は、多くが抱えているであろう、今日的な不安や不都合への処方箋とも言える。ここも実に今っぽい。
「遅れてきた思春期」に乗れるか、乗れないか
大きな山や谷もなく、穏やかに進むストーリーに、いったいどんなオチが用意されていたのか?
ドラマの宿命として、主人公たちは(良き方向に)変わらないといけないはずだが、このまま4人の馴れ合い、慰め合いで終わってしまうのか?
そんな疑問と心配を抱きながらたどり着いた最終回。
主人公たちは、気にしていたことの数々が解消され、顔が晴れやかになる。
その晴れやかさは、「気にするな」という否定ではなく、「それぞれを受け止めよ」という肯定からもたらされる。
そしてその肯定的な眼差しは、他者のみならず自分自身にも向けられている。ここが重要なポイントだと思う。
仮に世界に自分ひとりしかいないとして、そこに自分たるアイデンティティは確立し得ない。フェラーリにだって乗りたいと思わないし、エステに通ってキレイになりたいとか、幸せになりたいなんて考えすら及ばないかもしれない。
他者は自分をかたちづくる。
そして他者と自分の関係性は、自分が出発点になる。
自分を受け止められないひとが、他人を受け止められるはずもない。
作中に出てくる「2人組」という言葉には、ひとが他者と関わる上での最小単位という意味が込められている。他人と折り合いをつけることは、自分自身との折り合いから始まるということを知る、もっとも小さなユニットである。
4人の男女は、内部への優しい眼差しを獲得したことにより、外部との関係性を再構築していく。そういう最終回だったと思う。
そこにかすかな違和感を覚えるとしたら、内部と外部、自分と他者という問題意識は、一般には10代の頃に芽生えるものであるということ。そもそも「遅れてきた思春期」というテーマに乗れるか、乗れないかによって、本作の評価は分かれそうである。
藤井風『花』とSMAP『世界に一つだけの花』の、似てるようで違う世界観
今という時代を反映した『いちばんすきな花』。脚本も役者も観る側への誠意をもってつくられていたが、その白眉は、主題歌『花』を歌った藤井風だと思う。
ドラマの名前や歌の歌詞に触れて思い出したのが、2000年代初頭にヒットしたSMAPの『世界に一つだけの花』だった。ひとを花に喩え、一輪ごとに違う個性を認めよ、みな美しいではないかというメッセージは『花』と似ている。また2つの曲とも、「僕ら」という一人称複数で歌われている部分がある。とはいえこの2曲、与える印象が異なる。
『世界に〜』は、「ナンバーワンでなくオンリーワン」、つまり優劣などの第三者的な価値で比べても仕方がないんだと歌っている。ここでの「僕ら」は、社会や組織といった、より広い世界を相手にしている。“みんなの意識”に向かって訴えている。この曲が今でもテレビなどで好んで歌われるのは、この「僕ら」が及ぶ世界の広さが、より多くの共感を掴むのに役立つからだろう。
一方の『花』は、一人ひとりの心の叫びに対して作用するようつくられている、とても内向きな作品に感じる。
ここでの「僕ら」という言葉の意味は、限りなく英語の「I」に近い。
どう生きればいいのか悩み迷いながら、「咲かせにいくよ、内なる花を」と、自らに対して言い聞かせているように聞こえる。
「色々な姿や形に惑わされるけど」という歌詞も、惑わされている自分のことを歌っている。
個々人のなかにある弱さ、心細さに訴えかけるようだ。
「内なる花を見つけ、愛せよ」
『世界に一つだけの花』から『花』に至るこの20年で、広い外の世界から、それぞれの内側のより深いところへと目先が変化した。
この間、価値はますます多様化し、正論が蔓延り、ある特定の「正解」がなくなった。しかし、「正解がない=全て正しい」と言われたところで、果たして何を拠り所にして生きていけばいいのか?
このドラマが用意した答えは、「あなたの内なる花を見つけ、愛せよ」というメッセージだった。
『いちばんすきな花』は、2020年代の、生きやすいようで生きづらくもある側面を映した、実に今っぽい作品だったように思う。
■bg
reference
フジテレビ『いちばんすきな花』 Amazon Prime いちばんすきな花 シナリオブック 完全版(上) いちばんすきな花 シナリオブック 完全版(下) FOD