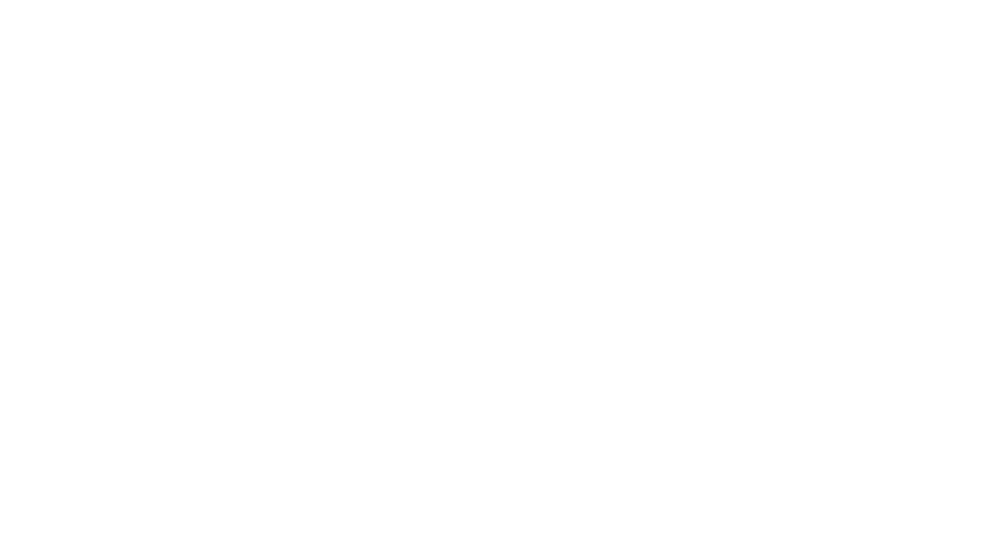いまのご時世、自動車やバイクに性的な意味を負わせることはできるのか?〜『あの胸にもういちど』で思ったこと〜

「失われた恋人が、ぞろぞろスマホの画面の中に出てくるという手酷さ」
ジャズミュージシャンで文筆家の菊地成孔が、著書『次の東京オリンピックが来てしまう前に』(平凡社)で、こんなことを書いていた。
短躯コンプレックスであることを自白する菊地は、ある時「レディスを身につける」ことに目覚め、とある女性向けの時計に一目惚れ。「身に着けに着けまく」るほど溺愛したものの、なんと3ヶ月で紛失してしまったという。
必死に探すも出てこず、路面店やメーカーに問い合わせるも見つからず、彼の心は諦めに向かっていた。そんな矢先、当時の妻から「メルカリ」の存在を教わることで事態は急転。菊地のアンチSNS、いやSNSのみならず、ネット社会全般に対する独特の嫌悪のようなものは知る人ぞ知る話であるが、検索するとお目当ての時計がずらり出てきたことに驚愕し、複雑な思いを抱いくに至ったという。
恋焦がれ、手に入れて、すぐに失い、探しまくって、諦めた菊地は、時計とのスマホ越しの再会に「ロマンもプライドもカシャリと砕ける音がした」と心情を吐露し、「もう一生会えない、追憶の中にだけ生きる筈だった、失われた恋人が、ぞろぞろスマホの画面の中に出てくるという手酷さ、それを買わずにはいられない自分、買って嬉しいかどうかすら予想できない自分」とその心境を綴っている。
結局、悩んだ挙句に購入したらしいのだが、そんな彼の葛藤は、なんでもネットで検索、なんでも見つけてしまえるネット社会では、すっかり忘れ去られてしまった情緒なのだろう。
フェティッシュな作品『あの胸にもういちど』
菊地が恋焦がれたレディス時計は、細身のケースに、バイクのチェーンを模したバンドが巻かれている「ディオール66」。これは1968年に公開された英仏合作映画『あの胸にもういちど』(原題:The Girl On A Motorcycle、仏語でLa Motocyclette)に登場する、ハーレーダビッドソンへのオマージュであるとされる。
『あの胸に〜』といえば、この映画に影響を受けた著名人は多いというフェティッシュな作品だ。主人公であるマリアンヌ・フェイスフル扮するレベッカは、『ルパン三世』の峰不二子のモデルとされた人物で、なるほど、レザーのジャンプスーツ姿でバイクに跨る不二子ちゃんのイメージと違わない。
婚約中でありながら、アラン・ドロン演じるダニエルと逢瀬を重ねていたレベッカ。実の夫をベッドに残し、全裸にレザーのスーツだけをつけ、ダニエルから贈られたハーレーを飛ばし、あれこれ妄想を膨らませながら、あの胸に飛び込もうと疾走。最後の衝撃的であっけないクライマックスに向かってスピードをあげていく。
バイクは自由と解放の象徴であると同時に、ダニエルのサディスティックな魅力、すなわち匂い立つ男性性やその延長にある暴力性などを暗喩として含んでおり、そんな彼に翻弄され軋むレベッカの心がスクリーンで描写される。
『男と女』と『ランデヴー』
こうした乗り物と性の比喩的表現は、クロード・ルルーシュの『男と女(Un homme et une femme)』(1966年)あるいは短編『ランデヴー(C’était un rendez-vous)』(1976年)などでもみられる。『ランデヴー』は、朝靄に包まれたパリ市内で、轟音を響かせて突っ走る1台のクルマを追った10分に満たない短編映画。信号をも無視する猪突猛進ぶりに最初は圧倒されるが、ラストでその問答無用の暴走のワケがオチとして用意される。女に会いに行くためにクルマを飛ばす男。特に年配の方なら、そうした構図にそれほど違和感を持たないはずである。
時は変わって現在。村上春樹の短編小説をもとに映画化された話題作『ドライブ・マイ・カー』にも、象徴的にクルマが登場する。あの「サーブ900」は、西島秀俊が演じる劇作家・家福悠介の愛車とされるが、劇中で運転するのは彼のみならず、ドライバーとしてあてがわれた三浦透子による渡利みさき、つまり女性もステアリングを握る。
ある特定の“性別らしさ”を求めるのははばかれる世の中になり、映画界でも人種的、社会的にマイノリティだったひとびとが主役に抜擢されるなど、政治的な正しさに照らし合わせた配役がなされるようになった。それはそれで歓迎すべきことであるが、自動車やバイクといったものに、性的な意味を負わせるということは、果たしていまでも通用するものなのだろうか。
ちなみに『あの胸にもういちど』は、Flick VaultというYouTubeチャンネルで無料公開されている。ネット時代、ロマンは希薄になったかもしれないが、過去の作品に触れる機会が格段に増えたのはいいところでもある。■bg
things to check