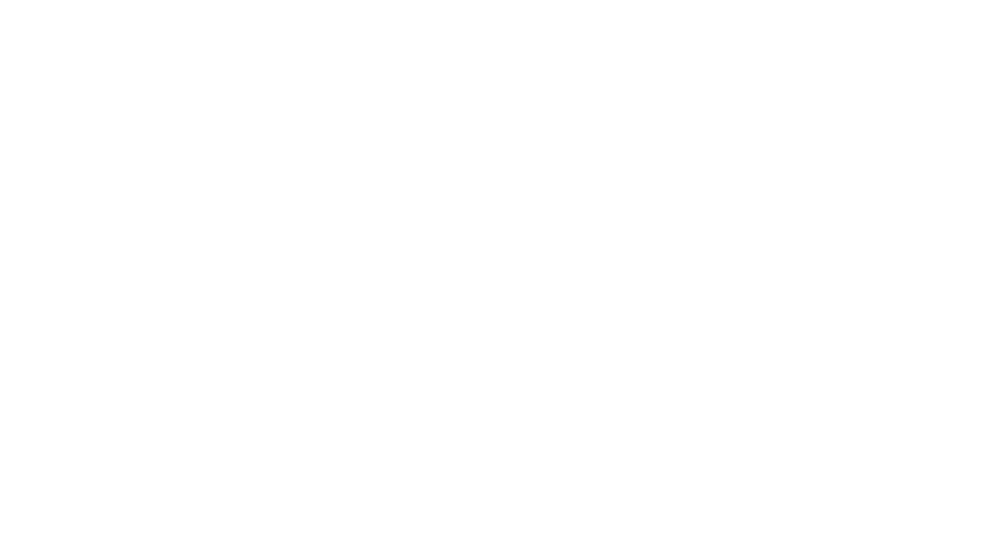スターバックス嫌いに「ジョイフルメドレー ティー ラテ」が教えてくれたこと
最多店舗を誇る「スターバックス」、だが……

愛用していた“常にあたたかいコーヒーが飲めるマグカップ”こと「Emberマグ2」の充電器がまたも故障した。とても気に入っていただけに(しかも1万円以上もするカップだし)意気消沈したことは言うまでもないが、「たまには外でコーヒーを楽しむのも悪くない」と思い直し、近場のカフェを探すことにした。
そこで、いまさらながら「スターバックス」の店舗が増えていたことに驚いた。
調べればチェーン展開するカフェとしては、「ドトールコーヒーショップ」の1070店(2023年12月時点)をおさえ、店舗数は国内最多の1885店(2023年9月時点)を誇るまでになっていた。東京なら、都心から郊外まで、お店を探すのにそれほど苦労もいらないほどだ。
しかし、である。
個人的にスターバックスはあまり好きではなかったのだ。
スタバの“ここが苦手”
まずは、あのちょっとスカした空気感である。やけに生き生きと働く意識高い系の従業員に加え、これ見よがしにMacBookやiPadを開く客層にも正直馴染めなかった。どこか「スタバを分かっているひとにしか分からない何か」という目には見えない壁を感じていた。
もっと言えば、「フラペチーノなんとかかんとか」なんていう、大の大人が口に出すのも恥ずかしい(と個人的には感じている)、まるで呪文のような商品名を口にしなければならないことには、困惑を通り越して迷惑でしかなかった。いろいろとカスタマイズでき融通がきくのはいいが、慣れてないと厄介で、間違ったらどうしようという無用な緊張をしいるし、そもそもどの組み合わせがいいのかは通じゃないと分からない。
近くて遠い場所、それがスタバ。
いっそのこと愛称が「スタコ」だったら、もう少し上手に愛せていたかもしれないのに(酢タコ、かわいいじゃない)。
冬の風物「ジョイフルメドレー ティー ラテ」との邂逅
そんなスタバで出会ったのが「ジョイフルメドレー ティー ラテ」。「この季節限定なんですよ」と、まだ20代のAさんに薦められて飲んでみたら、これがなかなか良いのである。

力強いブラックティーとウーロン茶のなめらかな甘さ、ジャスミンティーの花のような香りに、アプリコットの華やかな風味をアクセントとしたTEAVANA™「ジョイフルメドレー」にスチームミルクを注ぎ、ふんわりフォームミルクで仕上げました。(スターバックス コーヒー ジャパン公式サイト)
なるほど、フォームミルクのふんわりとした味わいとお茶のほのかな香り、シロップのかすかな甘味を楽しめるなかなかの逸品に、スタバの新たな一面を見た思いがした。
ジョイフルメドレー ティー ラテをはじめ、世界中には各国限定のドリンクが用意され、特にホリデーシーズンの限定品はひときわの華やかさを放つ。なるほど、企画としてもなかなかおもしろい。
「スタバってそんなに好きじゃなかったんだよね」と正直にAさんに伝えると、「店員もスマートでカッコ良くないですか?ちょっと憧れます」と無邪気に答えてくれた。
もちろん、苦手な理由のいずれも偏見ということは承知していた。
ただ今回、ジョイフルメドレー ティー ラテを通じて、少し見方が変わってきた。
スタバについて、何ひとつ知らなかったことに気がついたのだ。
スターバックスの“実質的創業者”の思い
遅ればせながら、『スターバックス成功物語』や『スターバックス再生物語』といった、スターバックスの実質的創業者であるハワード・シュルツの著書を開いてみると、スタバのここがちょっと……と思っていたことの数々には、背景があるということがはっきりしてきた。

シュルツは創業者ではなく、スターバックス自体は1971年にジェリー・ボールドウィンらにより興された企業だ。カフェ経営を伴う現在とは異なり、コーヒー焙煎などを手掛けるに過ぎなかった当時のスターバックスに、シュルツがマーケティング責任者として入社したのが1982年。その1年後、見本市のためイタリアはミラノを訪れたシュルツが、イタリアのエスプレッソバーでコーヒー文化を体験したことが、今日の世界的メガコーヒーチェーン店の“はじめの一歩”につながる。
帰国後、シュルツはイタリアンカフェをアメリカに持ち込もうとするも社内での理解が得られず、独立して自ら小売りコーヒー会社を設立。さらに程なくして古巣スターバックスを買収したことで、ようやく彼の夢は軌道に乗ることになる。
「ショート、トール、グランデ」の謎
かようにスタバとイタリアの浅からぬ関係については理解できたが、そこでいつも感じていた“かすかな違和感”を思い出した。飲み物のサイズ表記だ。一般に馴染みのある「S、M、L」ではなく、「ショート、トール、グランデ」と独特で、かつ英語、英語、突然イタリア語という妙な組み合わせに釈然としないものを感じていたのだ。
もちろん、イタリアのコーヒー文化に惚れ込んだシュルツのこだわりが、イタリア語のネーミングに至ったことは想像に難くないが、何とも中途半端な印象を与えるではないか。
とはいえ、「ピッコロ(イタリア語で“小さい”)」といったところで、お膝元のアメリカ市場では受け入れられない可能性もあっただろう。こだわりと現実主義の折衷がない限り、あれほどの企業規模に成長することはなかったはずである。
「フラペチーノ」は、コーヒー好きには邪道ではないか問題
もうひとつ、スタバで不思議だったのが「フラペチーノ」の存在だ。
Frappuccinoとスペルこそイタリア語っぽいが、そんなものイタリアにはないし、そもそもフランス語のfrappe(フラッペ)、イタリア語のcappuccino(カプチーノ)を都合よく合わせた造語である。コーヒーなどと氷をミキサーにかけた“氷菓子”、コアなコーヒー好きからしたら邪道ともいえるようなものが、なぜラインナップされているのか。
その誕生の顛末は、『スターバックス成功物語』に詳しい。アイディアを持ち込んだのはカリフォルニアの店舗担当者。当地の他店で暑い時期に冷たいコーヒー飲料が売れていたこと、またスターバックスでもコーヒーに他のものをブレンドした飲み物を希望するひとが増えていたことから、社内でテストが始まった。
当初、シュルツはこのフラペチーノの商品化に反対していた。「スターバックスの完全性を損なう製品であり、真のコーヒー愛好家に喜ばれる飲み物というよりはファーストフード店のシェイクのようなものだと思っていたのである」と前掲書にはある。
もともとスターバックスが1994年に買収したボストンの「ザ・コーヒー・コネクション」の商品だったフラペチーノは、試行錯誤の末、シュルツのゴーサインを得るまでのクオリティとなり、1995年に発売されると、翌1996年度には年間総収入の7%を占めるまでになった。
そして1990年代には2種類しかなかったフラペチーノは、その後スターバックスを代表する商品となり、「20億ドルの売り上げを誇る主力商品」にまでのぼりつめた。固定概念にこだわりすぎず、市場の風を的確に読んだ、ということだろう。
過去の失敗と成功
とはいえスターバックスとて、過去に失敗がなかったわけではない。ペプシコと共同開発した炭酸入りコーヒー「マザグラン」は、1994年に発売したものの不人気で姿を消し、また2008年に投入したイタリア生まれの冷たいドリンク「ソルベット」も空振りに終わった。
一方で、安かろう悪かろうのイメージが強かったインスタントコーヒーには、「VIA(ヴィア)」というブランドで2009年に市場参入を果たしており、こちらは現役商品としてラインナップされ続けている。
成功もあれば失敗もある。このことは、スターバックスがそれだけ商品開発で試行錯誤を続けているということの証左でもある。
そして、数あるカフェチェーンのなかで、フラペチーノほどの高い知名度を持つ商品も他にはない、ということも忘れてはならない。
スターバックスの価値が宿る“体験”
スターバックスは、ファーストフードやコンビニなどのエントリー向けではなく、またこだわりの高級店とも違う、ちょうど中間に位置するブランドであり、価格帯も若干だが高めに設定される。
しかし、仮にコーヒーの価格がコンビニと3倍違うとして、味が3倍良いとは言い切れないのが飲食の難しいところである。
では、スターバックスの、価格に見合った価値とは何か。
あの場所、あの対応、つまりすべての体験にこそ、スターバックスの価値が宿っている。
そしてその価値が一貫しているからこそ、人々はスタバにある種の共通したイメージを抱き、お店に足を運びたいと思うのである。
汚れていたり雑然とした店舗は一度として見たことがない。
やる気のなさそうな店員も皆無。カスタマイズに応えるだけの知識や技量がないといけないのだから、教育もちゃんとしていないといけない。
また1991年には、パートタイマーを含む従業員に自社株式購入権を提供する「ビーンストック(Bean Stock)制度」 をスタートさせている。企業として働きがい向上にいち早く取り組んでおり、こうした企業努力も従業員のやる気の源泉になっているかもしれない。

「ジョイフルメドレー ティー ラテ」が教えてくれたこと
そして今回、店の立地によって、実に幅広いひとたちが集う場所となっていることにも気がついた。
都心であればビジネスマンの止まり木、待ち合わの場所として使われているし、郊外であれば老人や学生の方なども多い。

東京の郊外、JR中央線国立駅内にある「スターバックス コーヒー nonowa国立店」では、ビジネス街にある店舗とは若干様相が異なり、地域のお年寄りや学生などが楽しげに語らうシーンを見かける。この店は、聴覚に障がいのある従業員を中心として、手話によるコミュニケーションを採り入れている日本初、世界でも5番目の「サイニングストア」。明るい店内には各所にサインが表示され、コーヒーを渡してくれる店員さんも手話で“話しかけてくれる”。
もちろん、こうした店舗を増やしていくにはなかなか難しいこともあるだろうが、社会課題に取り組む企業姿勢から応援したくなるような気持ちが芽生え、来店意欲にもつながれば、願ったり叶ったりである。
スターバックス嫌いに、冬季限定「ジョイフルメドレー ティー ラテ」が教えてくれたこと。
それは、多くの店にたくさんのひとたちが集まるという現象には、ちゃんと理由があるということ。
そして、知らないことを知るということの大切さであった。
まったくもって、食わずに嫌うな、ということである。
■bg