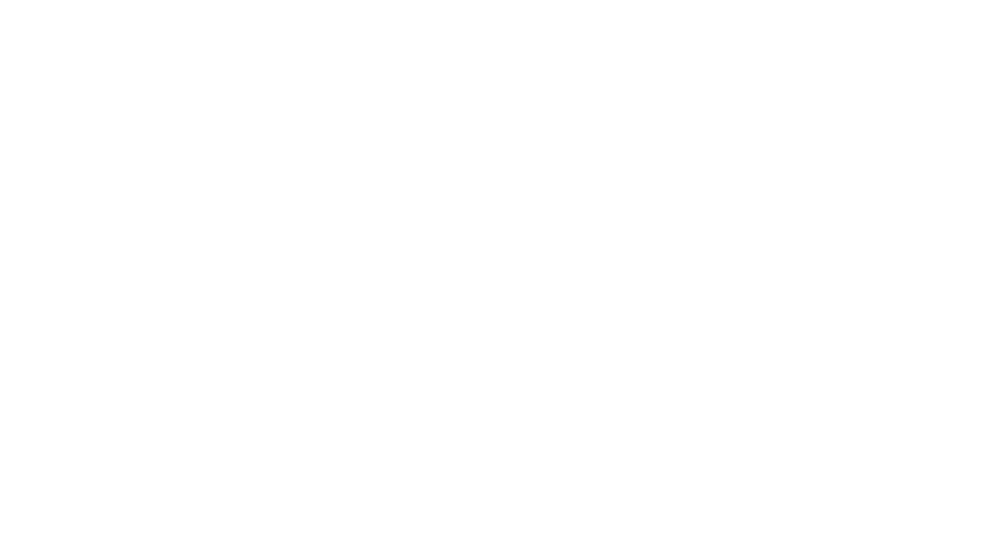第4章:時の「死角」~町田・大和・横浜での米軍機墜落事故~その4「横浜米軍機墜落事故」
1964年(昭和39年)に町田、大和と厚木基地周辺で立て続けに起こった米軍機墜落事故。その遠因としては、ベトナムでの米軍活動の活発化が考えられた。アメリカがベトナムへの大規模な軍事介入、いわゆる北爆をはじめるきっかけとなった「トンキン湾事件」は、この年の8月の出来事。その1ヵ月後に神奈川県大和市で墜落した戦闘機は、ベトナムから帰還したばかりのものだった。
天災は忘れた頃に、というのは人為的な事故についてもいえる。今回紹介する3つの墜落事故の最後「横浜米軍機墜落事故」は、過去の2つの惨劇から13年後、ベトナム戦争終結から2年経った1977年(昭和52年)に発生した。
巨大企業集合体「東急グループ」のはじまり
鉄道やバスなどの交通事業をはじめ、不動産事業、流通事業、ホテル・リゾート事業、さらには大型施設を抱えての文化事業 ─── 「東急グループ」の業態は実にバラエティに富んでおり、その総資産は2兆1486億円に達する(東京急行電鉄株式会社 平成29年3月期の連結会計)。たんなる鉄道会社の枠には収まり切らない、巨大な企業集合体である。
この「東急王国」の礎には、鉄道事業と連動するかたちで進められた、積極的な沿線開発の歴史があった。
東急電鉄の起源は、1922年(大正11年)9月に設立された「目黒蒲田電鉄株式会社」とされる。この時代、都市間交通を担う鉄道会社が数多く生まれており、目黒蒲田電鉄は、そうした鉄道会社を次々と吸収合併して規模を成長させていった。1939年(昭和14年)10月には「東京横浜電鉄株式会社」、さらに戦時中の1942年(昭和17年)5月には「京浜電気鉄道(現在の京浜急行電鉄)」、そして「小田急電鉄」を取り込み、名を「東京急行電鉄株式会社」と改称した。
京急や小田急、さらには後に加わる「京王電気軌道(現・京王電鉄)」と、関東近県の多くの私鉄を傘下に収めていた東急電鉄は、戦後の過度経済力集中排除法により大幅に再編されることになり、現在我々がよく知るかたちへと姿を変えていったのである(東京急行電鉄株式会社 会社案内)。
首都圏に広がる「田園都市」
東急電鉄のオリジンたる目黒蒲田電鉄は、1918年(大正7年)9月に設立された「田園都市株式会社」の鉄道部門が分離独立してつくられた。田園都市株式会社は、明治・大正を通じて日本の実業界を牽引した渋沢栄一らによって立ち上げられ、土地の分譲を事業ドメインとしていた。いまでいう「街づくり」事業のはしりである。街をつくるには人の移動を活発にする交通が必要だということで鉄道整備にも乗り出し、それが目黒蒲田電鉄の一部になった。東急電鉄のなかにある街づくりの概念は、しっかりとDNAに刻まれていたのだ。
そもそも「田園都市(Garden city)」とは、1898年にイギリスのエベネザー・ハワードが提唱したことで知られる都市形態で、簡単にいってしまえば大都市の周辺に設けられた衛星都市を指す。
東急電鉄が1953年(昭和28年)に発表した「多摩城西南地区開発趣意書」では、将来東京が過密状態になることを見越し、米英での衛星都市化を日本の首都圏で実現することが謳われていた。発表から3年後に具体的な計画が発表されると、多摩川西南部の4300ヘクタールものエリアを4ブロックに分割し、そこに40万人の人口を定着させようという壮大なプロジェクトの全貌は見えはじめた(『東急線各駅停車 城南・港北いま・むかし 首都圏沿線ガイド』石井恒男 他著)。
この計画にもとづき鉄道網も着々と整備されていった。1927年(昭和2年)開通した「二子玉川〜溝の口」をベースに、1966年(昭和41年)「溝の口〜長津田」が開通。その後、沿線に家々や街を造りながら線路は神奈川県下を突き進み、1984年(昭和59年)に「つきみ野〜中央林間」が完成。「渋谷〜二子玉川」の新玉川線を包含し、2000年(平成12年)に今日のかたちになったのが、その名もずばり「田園都市線」である。(東京急行電鉄株式会社 会社案内)。
前置きが長くなったが、今回の「横浜米軍機墜落事故」は、膨れ上がる首都圏の人口を吸収する受け皿として計画された、東急田園都市構想の開発地域内で起きた。
時は1977年(昭和52年)9月27日、場所は神奈川県横浜市緑区(現・青葉区)、田園都市線「江田駅」近くの、まだ開発途中の住宅地だった。
以降は、「町田米軍機墜落事故」、そして「大和米軍機墜落事故」と同様、『米軍機墜落事故』(河口栄二著)をもとに事故の顛末を振り返ってみたい。
40年前に起きた「横浜米軍機墜落事故」
アメリカではジミー・カーターが第39代大統領に就任、『スター・ウォーズ』の記念すべき一作目が封切られ、日本では王貞治がホームラン世界新記録の756号を達成、沢田研二の『勝手にしやがれ』やピンク・レディー『ペッパー警部』がヒット ── 1977年とはそんな年だった。東京オリンピックの年に起きた町田、大和の事故に比べれば最近とも思えるが、既に40年も前の出来事である。
事故現場となったのは横浜市緑区(現在の同市青葉区)。1966年(昭和41年)に開業した田園都市線「江田駅」から徒歩15分程度の場所だった。
この地域はかつて「小黒部落」と呼ばれ、すり鉢状の盆地に米や野菜を栽培する農地が広がっていたが、先に触れた東急の計画を機に開発の波に飲み込まれていくことになる。1964年(昭和39年)に国道246号線開通、その2年後に溝の口・長津田間の田園都市線開業、続いて東名高速道路の全面開通と、緑区周辺は数年間にわたり工事に明け暮れ、東京のベッドタウンとして急激な人口増加に見舞われていった。防衛省の資料「横浜市緑区への米軍機墜落事故への取組」にある事故直後の写真からも、宅地醸成中の雰囲気が感じ取れる。
9月27日火曜日、午後1時過ぎのことだった。厚木基地を離陸したばかりの米海軍第7艦隊空母「ミッドウェイ」に所属する「RF4Bファントム戦術偵察機」が、千葉県沖で待機していた母艦に向けて飛行している最中、エンジン火災を起こした。操縦士2人は緊急脱出を行い無事だったが、全長20m、重さ26トンを超える主のいない偵察機は燃料満載のまま墜落。家々を壊し、燃やし、そしてそこにいた人たちを傷つけた。
相次いで息を引き取った幼い男児たち
重傷者5人、軽傷者4人。うち重傷の4人は、現場から50m離れた場所で工事に当たっていた東急建設小黒作業所の社員が運転する車で青葉台病院に運ばれた。「全身熱傷三度」というもっとも重い診断を受けた4人には、すぐさま応急処置が施された。医師に「危篤状態も同然」と判断された3人のうち2人は、3歳と1歳の男児。年端も行かぬ子供たちは体表面積のほぼ100%で熱傷を負っており、また80%を火傷していた男児の母親も、開院から間もない昭和大学藤が丘病院で懸命の処置を受けていた。
昼下がりのひと時を過ごしていたこの親子と母親の妹は、墜落機のジェット燃料をもろに受け、爆風で一瞬のうちに吹き飛ばされ意識不明となった。しばらくして意識を取り戻した母親と妹は、「ママ、ママ」とうなされるように叫ぶ子供たちをかかえ、ガラスの破片を踏みながら炎から必死に逃げた。2mの段差を飛び降りた拍子に母親は骨折を負った。彼女の上半身に衣服はなく、スカートも燃え、下着だけのかっこうになっていた。
青葉台病院に担ぎ込まれた子供たちは、酷い火傷の痛みでもがき苦しんでいたため、ベッドから落ちてしまうのを防ぐために包帯で括り付けられていた。「これを取ってくれよ、取ってくれよ」「ジュースちょうだい」「痛いッ」。泣き叫ぶ小さな子供たちを、親族が泣きながらなだめた。やがて死期が近いことを示す嘔吐の兆候が見られ、深夜のうちに2人は相次いで息を引き取った。
事故から4年4ヵ月後、母親も息子たちのもとへ
この事故での死者は3人を数えるに至った。もう1人は、亡くなった男児たちの母親だった。
この事故で傷を負った他の被害者たちが徐々に快方に向かっている最中にも、生死の境をさまよっていた母親。腎不全、敗血症という危険な状況に、医師や家族たちは懸命に向き合った。さらに皮膚移植のためには大量の皮膚を確保しなければならなかった。皮膚集めに難儀していた医師たちに「新聞での皮膚提供キャンペーン」という提案を持ちかけてくれたのは、東京新聞横浜支局の若い記者。インターネットなどなかった当時、新聞という大メディアを使った声がけが奏功し、瞬く間に関東一円に住む471人の志願者が手を挙げ、善意の輪はその後も広がり続けた。
2週間に5回のペース、回数60回、針の数にして数万針超という、想像を絶する過酷な植皮手術を乗り越え、母親は医師から外泊許可が出るまで回復。時は1979年(昭和54年)の正月、事故から1年3ヵ月が経過していた。
ここで、これまで伏せられていた子供たちの死が、母親に初めて伝えられた。医師たちはショックによる自殺もあり得ると心配したが、家族や医師、看護婦たちのあたたかい看護もあって、母親はなんとか心の平静を保ちうるまでになった。
だが、一度狂った人生の歯車が元に戻ることはなかった。
その後の顛末は、毎日新聞の神奈川県版が2014年(平成26年)1月に組んだ特集「基地のあるまち」から引くことにする。
快方に向かっていた母親だったが、重い火傷、そして事故の精神的なショックから入退院を繰り返した。やがて、これまで懸命に支えてきた夫とも不仲になり、事故の4年後に離婚。それからしばらくした1982年(昭和57年)1月26日、治療の甲斐なく、息子たちのもとへと旅立っていった。事故から4年4ヵ月が経っていた。
横浜米軍機墜落事故で亡くなった3人の家族は、損害賠償で示談の道を歩んだ。愛息の死亡を知った時、母親は「2人をしっかり抱きしめてやりたかった」と呟いたという。その願いを叶えようと、家族は裁判で争うよりも、3人の像の建立に力を注いだ。横浜市中区の「港の見える丘公園」の母子像は、1985年(昭和60年)1月に除幕された(毎日新聞神奈川版【基地のあるまち 第1部・犠牲 11「母子像」に託す思い】2014年1月15日付)。
林和枝、長男の裕一郎、次男の康弘の親子3人は、公園の木々の下で肩を寄せ合いながら、いまも港の景色を眺めている。
法廷で争うことを選んだ家族
この横浜米軍機墜落事故にはもうひとつの側面があった。法廷での事故の責任追求だ。
自宅が全焼し、妻が重傷を負った別の家族は、1980年(昭和55年)9月に横浜地裁に提訴。日本政府のみならず、墜落機を操縦していたパイロットら米兵2人をも相手取った。日米安保条約の詳しい取り決めが記載される「日米地位協定」では、公務中犯罪の第1次裁判権はアメリカ側にあるとしているが、日本の民事裁判権の完全免除までは規定していない ── これまで日米地位協定を盾にアメリカの責任を曖昧にしてきた日本政府に叩きつけた挑戦状だった。
提訴から6年半後の1987年(昭和62年)3月に出た判決は、国が主張した1426万円を大幅に上回る4580万円の賠償を命じるというもの。米兵への請求は棄却したものの、「完全免除を規定する条約はない」として、公務中の米兵も日本の民事裁判権に服するという画期的な判断だった。国は提訴しなかった(毎日新聞神奈川版【基地のあるまち 第1部・犠牲 11「母子像」に託す思い】2014年1月15日付)。
被害者の舘野正盛が、まさに身命を賭して戦わざるを得なかった大和米軍機墜落事故の時は、法整備も、また世論も、駐留米軍の事故と向き合う準備が整っていなかったのかもしれない。時代の変化を感じさせる判決となった。
40年後、事故現場で見た「風景」
東急田園都市線の江田駅を降りると、起伏ある地形の上に、計画的に整理されたことが見て取れる新興住宅地然とした街並みが広がっていた。40年も経てば事故の痕跡など見つけることは期待できないが、当時どのように開発されていったかという人為の営みはひしひしと伝わってくる。
かつてハワードが提唱した「田園都市」は、都市の周辺にある自然豊かなエリアに、職住が近接した、自給自足の生活環境を築いていくというものだったが、東急がつくりあげた田園都市は、東京という大都市に接続する「寝る場所」、つまりベッドタウンの域を出ていない風情である。
もちろん、そうしたベッドタウンのあり様を否定するつもりはない。東急の田園都市構想があろうがなかろうが、東京を中心とする首都圏に押し寄せる人々の波が途絶えることはなかったはずだし、こうした人口移動のダイナミズムが、戦後日本の復興と成長を支えてきたことは事実である。日本における田園都市は、一方で巨大な経済圏を成しながら、他方では、名もなき市井の人々の暮らしの場として機能してきたのだ。
事故現場といわれる場所には、小さな公園がある。冬の午後に訪れると、そこでは小学生の男の子同士が遊具に腰掛けて学校の話に興じていた。ここは厚木基地から直線距離で15km程度離れているというが、私がその場にいるうちは軍用機らしきものを確認することはできなかった。
ありふれた日常を切り取ったかのような、平和といえば平和な一瞬。しかしそれは、平和というフィルターを通した景色であり、仮にここに事故の遺族がいれば、また別の世界が広がるのだろう。
私は遺族や関係者ではないものの、この事故については個人的な思い入れがあった。
40年前の事故当時、私自身も横浜に住んでいた。近くで飛行機が落ちたと、母から聞いた3歳の時の記憶がいまも残っている。
そして、この事故で亡くなった長男と私は同い年だったという事実も、思い入れの源泉となっていた。もし彼が事故に巻き込まれていなければ、結婚し子供が生まれ、という、私と同じような人生を歩んでいたかもしれない。あるいは、事故に遭うのが自分だった可能性だってあっただろう。様々な思いが交錯し、何ともいえない複雑な心境になるのだ。
本章のタイトル「時の死角」は、時間の経過が作用して見えなくなる過去の事実、という意味でつけたものだが、こと横浜での墜落事故が起きてからの40年は、私にとって死角をなしていないのである。
さらに、私もひとの親となり、子を失うつらさに敏感にならざるを得なかったということもあった。『パパママバイバイ』 (早乙女勝元著)など、この事故に関する書籍が多く残されているのだが、そこに綴られる非情なまでの状況に触れるたび、目頭が熱くなることが多々あった。
当然、こうした私の心のなかの動きなど、目の前の公園で遊んでいる子供たちは知らない。そもそも、彼らが生まれるとうの昔にここで起きた惨事のことなど、気にかけたことがないかもしれない。
私が事故現場で見たのは、こうした個人の経験や想いから立ち現れる「風景」だった。
「風景」とは、ひとによって違って見えるもの。
私が探し歩いたのは、こうした風景のなかに潜む「死角」だった。■ bg
(続く)