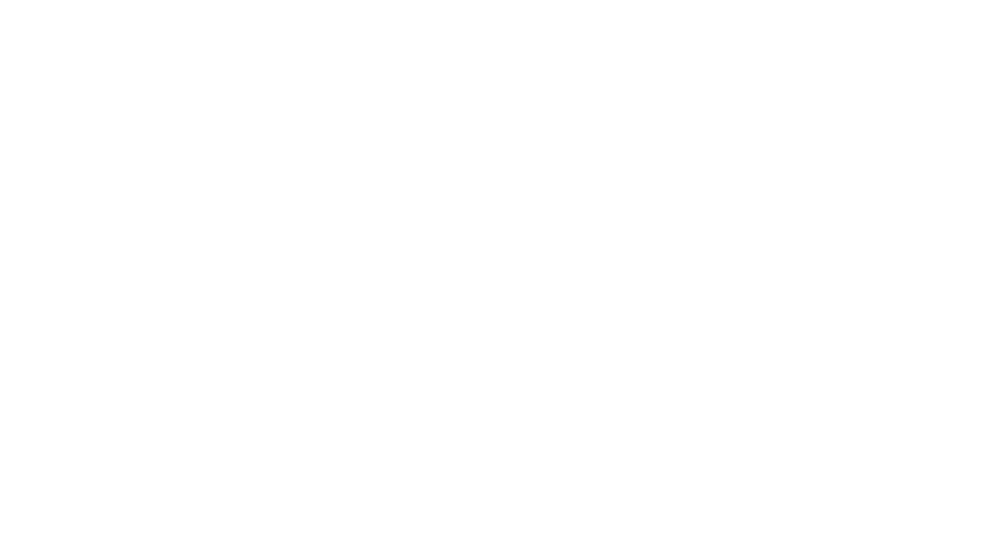最終章:追い続けてきた「風景」
東京にいて基地問題を考えるというテーマを「死角と構造」と題して連載し、これまで東京西部の立川基地と横田基地を取り上げ、日米安保体制における東京の役割について触れ、さらに時計の針を数十年前に戻し、神奈川県の厚木基地周辺で起きた3つの米軍機墜落事故を掘り起こしてきた。12回目にして最終回では、連載しようと思った経緯や狙いについて触れ、締めくくりたい。

厚木基地(撮影=bg)
「現場を訪れる」というアイディアのもと
前口上『東京にいて「平和憲法」や「沖縄の基地問題」を声高に訴えるバツの悪さ』を公開したのが2015年6月のこと。あれから3年、テーマを思いついてから4年の時間が流れた。書きはじめた当初は、戦後70年の節目にあたり、安保法案、集団的自衛権の話題でメディアは持ちきりだったが、いまではそれらの名前を目にすることもすっかり少なくなった。テーマで取り上げた事象の実情は、あれからそれほど変わっていないように思えるが、世相はかように移ろいやすいということか。
「死角と構造〜東京で基地を考える〜」を書くにあたり、資料や書籍のみならず、実際に現地に足を運んでみる手法を取ることにした。このアイディアは、武田徹『暴力的風景論』から拝借したものである。
武田は本書の冒頭で、戦後日本を震撼させた「出来事」や「事件」が起きた現場 ─── 沖縄の米軍基地、連合赤軍事件が起きたあさま山荘、オウム事件とサティアンがあった富士山麓、酒鬼薔薇聖斗事件と神戸など ─── を訪ねようとしている、とはじめる。そしてその目的は、たんなる物見悠然ではなく、『「風景」を見るため』だとした上で、こう続けた。
2011年3月11日、東日本大震災とこれにともなう福島第一原子力発電所事故を境に、「日本は変わった」とよくいわれた。しかし、これまで大事件や災害が起こるたびに「これで日本は変わる」といわれながら、時間の経過とともに平穏を取り戻し、結局、社会は何も変わっていなかったということがいかに多かったか。甚大な被害が出たとしても、いつしか忘れ去られ、切り捨てられた犠牲者が、かえって不遇になることもあったのではないか。
こうした「日本は変わった論」、より具体的には、福島原発事故後の放射能汚染を巡る「放射線過剰忌避言説」 ─── あの事故をきっかけに、ゼロベクレルあるいはゼロリスクを希求し、政府や電力会社を一方的に批判し、福島はひとの住める場所ではないと決めつけ、住み続けるひとすら非難し、さらに福島由来のものを徹底的に避けようとする ─── に違和感を覚えた武田は、こうした他者の存在を認めていないかのような言説空間にいる人々が、「風景」を見ているということに気がついた。
現実そのものを隠してしまう「風景」
ここでいう「風景」とは、津波に襲われ壊滅的被害を受けた被災地の様子や、水素爆発を起こした原発という実在するものというよりも、自分たちの「気分」であり「世界観」であり、そして「物語」のことである。
「風景」には、もうひとつ重要な特徴がある。自分に見えている「風景」しかその人には見えないということだ。「風景」とは、その人が見ている世界そのものである。「気分」の産物であり、「内面」の反映であり、「物語」を構想する想像力によって作り出された「世界観」や「歴史観」に通じる性格を持っている「風景」がひとたび視界に現れれば、人はそれ以外のものとして世界を見ることができなくなる。こうして「風景」は顕現すると同時に、隠蔽もする。そのようにしか見えない「風景」は、それ以外の「風景」や、更には現実そのものを隠してしまう。(『暴力的風景論』10ページ)

府中基地(撮影=bg)
「核」に近ければ近いほど(質的にも)穢れ、離れれば離れるほどユートピアの様相を呈している世界観のなかでは、穢れてしまった世界を浄化するために、3.11以降の日本を変えていくための改革を声高に訴えることは正当化される。しかしそこには、こうした主張がもたらすかもしれない福島差別などの負の部分はなきものとされてしまう。
かように「風景」は「暴力」の源泉となる。だからこそ「風景」に惑わされないために、自分にはそうとしか見えない「風景」と距離を置き接することはとても重要なのだ。
こうした武田の主張に触れ、私自身も身に覚えがないわけではなかった。「放射線過剰忌避言説」に片足を突っ込んだ記憶と、その後、反原発デモを通じて感じた淡い失望感、社会運動のあり方への懐疑が思い出された(反原発デモの話は別のブログ記事に詳しい。あの時も武田の本から大いに影響を受けた)。
また、原発事故から7年以上経った2018年8月、JR福島駅前に巨大な子供の像「サン・チャイルド」が建てられたことを発端とした炎上は記憶に新しい。
芸術家ヤノベケンジによるその像は、黄色い放射線防御服にヘルメット、胸に「000」と表示されたガイガーカウンターと、明らかに原発事故を想起させるもので、住民からの強い反対もあり、市は早々に像の撤去を決めた(朝日新聞デジタル『防護服着た像、福島市が撤去へ 「賛否分かれ設置困難」』2018年8月28日付)。
復興や再生、希望といった「サン・チャイルド」に込められた想い、つまりはひとつの「風景」が、別の「風景」(事故後様々な誤解やデマにさらされ続けたひとたち)と衝突した。美術館などクローズドの空間ではなく、多くが日常的に訪れる駅前という公共空間に(ある意味、暴力的に)一方の「風景」が具現され、晒されたことで、炎上の度合いは増すこととなった。像を建てる側に、異なる「風景」への認知がもう少しあったら、その先の展開は違っていたのではないか ─── 「サン・チャイルド問題」を「風景論」で解するとこうなるだろうか。
「風景」と距離を置くこと
「風景」から視線をずらすと、どんな世界が見えてくるか。今回の「東京で基地問題を考える」というテーマでも、歴史を掘り起こし、なるべく史実を史実として受け止め、そして当時そこにあったであろう「風景」がどのようなものだったのかを意識して確かめようとした。ゆえに「在日米軍基地=反米、対米従属」といった紋切り型の思考は極力排除し、なるべくニュートラルに、淡々と調べ、現場を訪れ、書いてきたつもりである。
実際にその場に行ってみると、その都度、本で調べた時とは異なる印象を受けた。
いまは自衛隊の基地である立川基地の北部、かつて激しい抗争が起きた砂川地区には、運動の痕跡がいわば亡霊のように街並みに溶け込んでいることに驚いた。運動そのものは既に過去のものとなっていたが、基地の目の前で、日本やアメリカという国家に向かってノーを突きつけてきた人たちの怨念のようなものがこびりついている、そんな場所に見えた。私自身は沖縄に住んだことがなく、基地から縁遠いと思っていたが、ごく身近に起きたこうした反対運動の軌跡を辿ることで、運動の成り立ちやその後をなぞることができた。
また関東計画で首都圏の基地機能を引き受けることになった横田基地周辺も、基地を中心とした街づくりに励むひとたちもいれば、国からの交付金で立派な市庁舎が建つなど基地を積極的に受け入れている姿勢も感じられた。基地があることが悪にもなれば、ある意味で善にもなるという「風景」を認識した。(第2章 その1、その2、その3、その4)。
一方で、厚木基地周辺を訪れてみると、いやいや首都圏にも現在進行中の基地問題があるんだと気付かされたりもした。戦闘機の爆音のなか日常生活を送る人々、そして過去に米軍により起きた悲惨な事故の犠牲になったひとたちの「風景」を想像してみた。自らの幼少期の記憶として残る「横浜米軍機墜落事故」の現場では、幼くして亡くなった当時3歳の「同級生」に思いを馳せ、「大和米軍機墜落事故」の慰霊碑には、ある種の無念さを感じた(第4章 その1、その2、その3、その4)。
東京にある米軍関連施設は、いずれもひっそりと、意外な場所に存在していた。しかし見えづらい「死角」にあるからといって、瑣末な扱いを受けているわけではなさそうである。米軍基地が沖縄に集中していることはよく知られているが、都内の米軍施設は、日米安保の(あるいはアメリカ外交上の)頭脳的な役割を担っているということであり、そうした安全保障上の仕組みそのものが日本全体に根付いていることを感じさせる「風景」だった(第3章)。
こうした一連の取材を通して実感したことは、物事は複雑に絡み合い、様々なレイヤーにそれぞれの思惑や感情があり、是なのか非なのかをジャッジすることは簡単ではない、ということだった。
私のなかにも、自分なりの「物語」を通した「風景」がかたちづくられているはずである。
しかし、それぞれの「風景」そのものを否定してはならない。大切なのは、自分とは違った「風景」を見ているひとがいるということを認めること。そうした「風景」が、どんな出来事や状況でかたちづくられていったかを検証してみることなのではないだろうか。
■
「軸がぶれない」とは、スポーツなど身体を動かす際にも、またひとの生き方にも使われる表現だ。どちらにせよ立派な褒め言葉に聞こえるが、軸が定まっていること自体がいいのではなく、その軸を中心に力強く、しなやかに動くことが肝要なのである。
原発や日米安保。賛成や反対があっていい。
しかし、是だろうが非だろうが、それぞれの主義主張に固執し過ぎれば、社会そのものの発展の妨げになることもあるし、それゆえに無意識にひとを傷つけることもある。
是と非の分断から、社会を前進させることは容易ではない。
様々な「風景」を追いかける旅は、まだ終えるわけにはいかない。■ bg
(連載終わり)