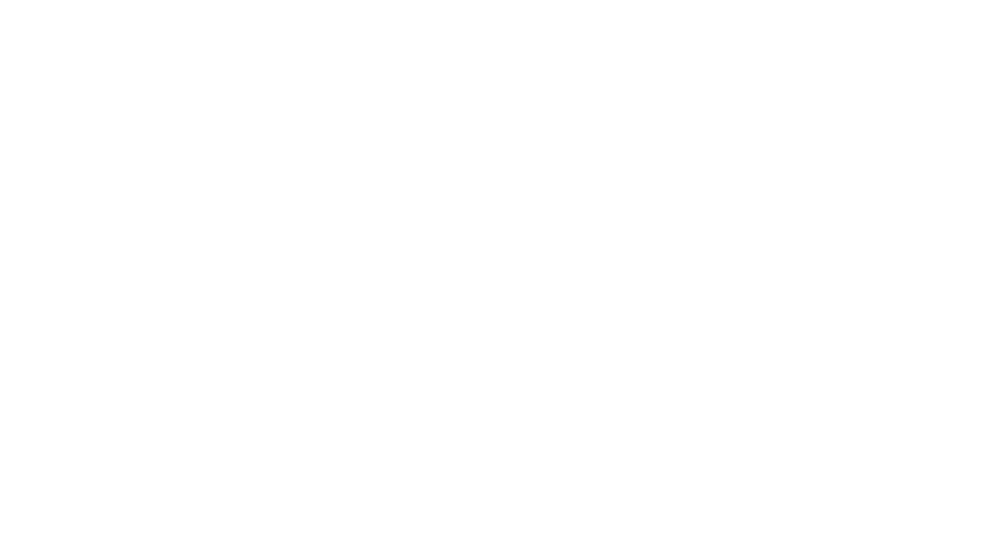ケータイがもっとも個性的だった時代〜エリクソンER205&ノキア7600が教えてくれること〜

ケータイ初号機の“失敗”
1990年代は“一億総通信時代”の幕開け。インターネット、そして携帯電話が我々の生活を次々と変えていく時期だった。ちょうどその頃に青年期を過ごした筆者も、大学入学前の1993年にポケベル(ポケットベル)を契約し、翌年にはパソコンを買ってEメールをはじめ、そして卒業間近の1997年には、念願だったマイ・ケータイを手に入れた。
記念すべきケータイ初号機は「NTTドコモ デジタル・ムーバD203HYPER」。フラップを開くとボタンがあらわれる三菱電機製の端末だった。選んだ理由はいまとなっては忘れたが、残念ながらあまり気に入らなかったということは覚えている。ケータイを持つ喜びの方がまさり、端末の良し悪し、特にそのルックスについてはあまり頓着しておらず、使い続けていくうちに飽きがきてしまったのである。

というか、この端末だけが悪いわけではなかった。店頭に並ぶ機種はどれも似たようなもので、おしなべて、上からアンテナ、受話口、単色の液晶画面、アンサーキーに番号ボタン、送話口が連なり、パッとしない事務的な顔つきのものばかりだった。
デザインにすぐれたケータイを探しはじめて数ヶ月。秋葉原の電気街で、ようやく「これだ!」と思える機種と、奇跡的な出会いを果たすことができた。
北欧からきた限定商品「エリクソンER205」
通信インフラメーカーとして世界的に名が通るスウェーデンのエリクソン社は、一時期、携帯電話端末も製造していたのだが、同じ北欧のフィンランドを本拠とするノキアの急成長を受け、この分野では劣勢に立たされていた。
状況を打開するため、2001年、やはり携帯電話事業では弱小だったソニーとタッグを組んで合弁会社「ソニー・エリクソン」を設立。しかしこのパートナーシップは、その後急拡大したスマートフォン市場でプレゼンスを出せずに2011年で解消され、エリクソンは端末事業から撤退を余儀なくされた。
そんなエリクソンが、単独で市場調査用に日本に送り込んだモデルが、カタログ名「DoCoMo by ERICSSON ER205」こと「エリクソンER205」。1998年に発売された限定商品であった。

ER205のセリングポイントは、何をおいてもデザインだ。当時のパンフレットには、「誰よりもエレガントな携帯を持ちたかった。」と、まるでこちらの心情を代弁するかのようなコピーがあり、「シンプルを極めた機能美と使いやすい操作性を合わせ持つこと」が「スウェディッシュ・デザイン」であると謳われる。
表を深い青、バッテリーを含めた裏側を黒とした渋い配色、単色のディスプレイの下のフリップを開けると、艶消しの黒いボタンがかしこまって配置されている。他の国産メーカーのデザインが劇画調の子供騙しに見えていた筆者には、エリクソンのシンプルで落ち着いたルックスがとにかく新鮮だった。
秋葉原のソフマップで、なんと1台1890円という破格の値段で売られていたため、2台購入して1台を未使用のままキープ。もう1台は、常に革製のケースに入れ丁重に扱いながら、6年もの間使い続けた。いまもなお、我が人生における“ケータイの殿堂”に入る、自慢の名機として手元に残している。



件、着信音選択6種類+7曲+オリジナル着信音、着信バイブレーター、ショートメールなど。(撮影=bg)
2000年代、時代はデザインケータイへ
ケータイでデザインが注目されるようになったのは、2000年代に入ってから。カラーズ編著『携帯電話のデザインロジック―電話を超えた万能ツールはどのようにデザインされるのか?』(誠文堂新光社)では、いわゆるデザインケータイを手がけた佐藤オオキ、佐藤可士和、深澤直人といった著名プロダクトデザイナーたちが、開発の経緯やデザインの考えなどをインタビュー形式で話してくれている。サブキャッチにある「デザインで携帯電話の新時代を切り拓くトップデザイナー10人の想いと狙い」という言葉からも、各キャリアがデザインで勝負していた当時の様子をうかがい知ることができる。
デザインケータイで先鞭をつけたのは、KDDIの「au」ブランドだった。2001年にプロトタイプ版発表、その2年後に製品化された深澤直人の手による「INFOBAR」を皮切りに、マーク・ニューソンのポップでフラットなデザインが特徴の「talby」(2004年)、サイトウマコトによる楕円形の斬新なカタチをした「PENCK」(2005年)、見かけのみならず触感にもこだわった吉岡徳仁の「MEDIA SKIN」(2007年)と、au design projectと銘打たれた一連の商品が次々と生み出され、他社もそれに追随した。
こうしたauのデザイン戦略はブランディングの一環だったと前掲書にある。DDI、KDD、IDOの3社が合併し、auブランドのもと2000年にスタートをきったKDDI。合併直後の黎明期にあって、ブランドとしての方向性を示す方法とされたのが、デザインだった。
だが一方で、世の端末が奇抜な衣装を纏いはじめた2000年代は、携帯電話業界全体が、差別化の要因としてデザインを求めていた時代でもあった。
電話から情報端末へ
総務省が発表する情報通信白書によると、1990年代に爆発的に普及した個人所有の携帯電話は、大きく4つの時期に分けられる。
| 1993年頃まで | 移動通信サービス黎明期 |
| 1993年頃から1998年頃まで | 携帯電話普及開始期 |
| 1998年頃から2008年頃まで | フィーチャーフォン全盛期 |
| 2008年頃以降 | スマートフォン登場・普及期 |
上記の普及開始期にあたる1994年、それまで保証金を預けてレンタルするしかなかった携帯電話端末が「買い切り制」に移行すると、ポケベルからPHS、そして携帯電話へと流れるトレンドに勢いがつく。この間に様々な携帯電話キャリアが誕生し、やがてデジタル技術による通信環境のクオリティが安定すると、今度は各社差別化のために、工夫を凝らしたサービスや端末が次々と生まれることになった。

1999年2月、NTTドコモによる「iモード」サービスがスタート。たんなる電話から情報端末へと軸足が移り、さらにカメラや決済、ワンセグ携帯によるテレビ受信など機能も充実していく。こうした端末の商品性のなかに、デザインも組み込まれるようになったのが、ちょうど2000年以降ということだったのだろう。
そんな折、とびきり奇抜な衣装を纏った舶来品「ノキア7600」がやってくる。2004年のことだった。
“携帯電話界の巨人”だったノキア
北ヨーロッパを指して「北欧」と呼ぶのは周知の通りだが、当然ながら国や地域によって歴史的、文化的な差異が存在する。
なかでもフィンランドは、いまでこそ高い教育水準や充実した福祉政策、さらには「マリメッコ」や「ムーミン」といったカルチャーアイコンでも有名だが、1917年に独立した比較的若い国であり、また隣り合うスウェーデンに600年、ロシアに100年も統治されてきたという数奇な国史を持つことはあまり知られていないのではないだろうか(石野裕子著『物語 フィンランドの歴史 – 北欧先進国「バルト海の乙女」の800年』中公新書)。
日本よりやや小さい33.8万平方キロメートルの国土は約7割が森林で、その資源を最大限に活用した林業や製紙業が発達した。1865年創業の「ノキア」の興りも製紙業からであり、当初はゴム長靴やタイヤ、電線などを手掛けていたが、1970年代から1980年代にかけて電話交換機を発明すると通信事業を生業とするようになり、世界企業として大きく飛躍することになる。
成長の勢いは国家規模であらわれ、石野前掲書によれば、最盛期の2000年にはフィンランドのGDPの4%を占め、ノキアの携帯電話生産台数は2010年まで世界一だった。列強のはざまで揉まれ、アイデンティティを模索してきたフィンランド人にとって、ノキアはナショナルプライド、国威であったといっても過言ではなかった。
携帯電話の雄として名を馳せたノキアは、しかし、日本では国産メーカーに押され地味な存在だったと言わざるを得ない。世界の多くで採用されていた通信規格「GSM」が日本では使えなかったこともあり、主に海外渡航社向けのモデルとしてのポジショニングにとどまっていたことは、国内販売チャネルとして成田や箱崎に店舗があったことからも想像できる。
そんなノキアが、2004年に鳴り物入りで日本で発売したのが「7600」。我が人生3機目のケータイ、そして2機目の北欧デザインの端末であった。
「ノキア7600」に見た、スマホへの萌芽
「ノキア初の日本語対応3G端末」と謳われる7600は、日本のWCDMA規格と海外のGSM規格で使えるデュアルモード対応の機種であり、日本でも海外でも使えるという点がいかにも国際ブランド、ノキアらしかった。
だが、やはり最大の特徴といえば、もはや電話とは呼べそうもないそのカタチだ。平行四辺形のような木の葉型をしており、中央に6万5536色表示のカラーディスプレイ、その左右に数字キー、下にアンサーキーなどが配される。

この独特のフォルムについては、7600のデザインを担当したノキア・インダストリアルデザイナーのテジ・チャウハン氏の記事に、興味深い箇所を見つけることができる。同氏は、より高速な通信が可能となる「3G」導入により、音声中心のコミュニケーションからビジュアルを用いたリッチなものに変わっていくとし、それゆえに「ディスプレイがデザインの中心になってほしかった」と語っていた(ITmedia『モダンとエスニックの融合~デザイナーが語る「Nokia 7600」』2003年10月15日付)。
音声通話のための電話から、情報端末へと変わるケータイ。より多くの情報を扱うことを前提に、ディスプレイの重要性が意識されていたのである。数年後に到来するスマートフォン時代への萌芽を感じさせる、そんなエピソードだ。
機能的に見ても、7600はいわゆるマルチメディアの活用が前提とされていた。写真やビデオの撮影はもちろん、POP3/IMAP4対応のメール送受信、MP3/AAC対応のミュージックプレーヤーに標準装備のイアフォン、XHTML対応のブラウザ、そしてBluetoothと赤外線によるワイヤレス接続と、当時としては充実した内容だった。
さらに、ライフスタイル路線も志向されていた。端末のフチの部分は、付け替え可能な「Xpress-on Sleeves(エクスプレス・オン・スリーブ)」と呼ばれるカバーが備わり、別売りのスリーブで見栄えを変えることができた。また端末の販路でもあったBEAMSからは、ブラックレザーのキャリング・ケースを発売するなど、たんなる通信端末の枠を越えた、ファッションの一部としてケータイが置かれていたことも特徴的だった。



ケータイがもっとも個性的だった時代
エリクソンに心酔した時から幾星霜。スマートフォンというエポックメイキングな端末の登場と、通信やその他技術の革新により、我々の日常は大きな変貌を遂げた。SNSなどのコミュニケーションサービスや多様な決済手段など、いまやこれなしに社会は成り立たないといってもいいぐらい、携帯端末への依存度は格段に増した。
こうしたスマホ時代に一石を投ずるべく、2021年に日本の家電メーカー、バルミューダが「BALMUDA Phone」なるスマホを出して話題となった。同社の寺尾玄社長によれば、「現在のスマートフォンが画一的で、選択肢が少ないと長年感じてきたこと」がBALMUDA Phoneをつくろうと思った理由のひとつだったという(バルミューダ「BALMUDA Phone開発ストーリー」より)。
20年以上前、筆者が感じていたような「選びようのなさ」。たしかにスマホはどれも似たようなカタチであり、そんな景色に既視感がないわけではない。しかし、1990年代末に味わったような違和感は、個人的にはない。
BALMUDA Phoneは、10万円を超える高級機ほどの価格帯ながら、画面が小さい、スペックが劣るなど芳しい評価を得るには至っていない。ソフトウェアを含め独自の意匠にこだわった結果、コストに跳ね返ってしまったということであろう。
このバルミューダの一件は、ケータイのデザインのあり方の変容をあらわしていたように思うのだ。スマホと従来のケータイ、同じ通信端末の、同じデザインという評価軸ながら、その領域は以前よりも格段に広くなった。外観や内部のソフトウェアの美的な意匠がデザインされた時代はとうの昔に終わりを迎えており、いまやユーザーの生活、経験そのものがデザインの対象となっているのである。
アップルのスティーブ・ジョブズが残した次の言葉は、今日的なデザインを考える上で示唆に富んでいる。
「デザインを外見と捉えるのは間違いだ。<中略>みんなはデザインをお化粧だと思ってる。ハコを渡して『見栄えをよくしてくれ』と言えばいいと思ってるんだ。それはデザインじゃない。外見と感覚だけじゃないんだ。デザインは、ものの働きなんだよ」(リーアンダー・ケイニー著『ジョナサン・アイブ』日経BP社)
スマホ時代を牽引してきた「iPhone」を長年使い続けてみて、「デザインはものの働き」とするジョブズの考えには納得せざるを得ない。iPhoneの無駄のない、洗練された外観のなかには、アップルが張り巡らすネットワークが広がり、「MacBook」や「Apple Watch」「iCloud」「Apple Pay」といった製品やサービスがシームレスに連動してユーザーの生活をサポートしてくれる。もはや見栄えがいいというだけでは、デザインは語れないのだ。
そして、市場で戦いを繰り広げる役者も様変わりした。かつて世界一を誇ったフィンランドの巨星ノキアは、スマホの潮流に乗り遅れ、エリクソンと同じように通信インフラ業者へ転身した。ノキアが去ったマーケットでは、アップルやサムスン、シャオミといった新たなメーカーがしのぎを削っている。劇的な趨勢の変化である。
こうしたデザインをめぐるケータイ小史を踏まえつつ、あらためてスマホ以前を振り返ってみると、2000年代は、もっともケータイ(の形態)が個性的だった時代、誰もがその意匠を一目見てときめき、胸躍らせることができた時代だったということに、気がつくことだろう。
デザイナーたちのクリエイションの結晶、色とりどりのユニークなカタチで賑わいを見せたあの頃。いまも手元に残る、かつて愛用した2台の北欧生まれの端末が指し示すのは、短くも長い携帯電話の歴史の、絢爛なる1ページであった。■bg

things to buy




reference
- au design project https://time-space.kddi.com/adp15th/
- 総務省 令和元年版「情報通信白書」携帯電話の登場・普及とコミュニケーションの変化 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd111110.html
- ITmedia『モダンとエスニックの融合~デザイナーが語る「Nokia 7600」』2003年10月15日付 https://www.itmedia.co.jp/mobile/0310/15/n_design.html
- ケータイ Watch「国内基地局ベンダシェアは北欧勢が半数超占める、国内ベンダの復活は?」2021年3月23日付 https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/mca/1313307.html
- Ericsson https://www.ericsson.com/en
- Nokia https://www.nokia.com/