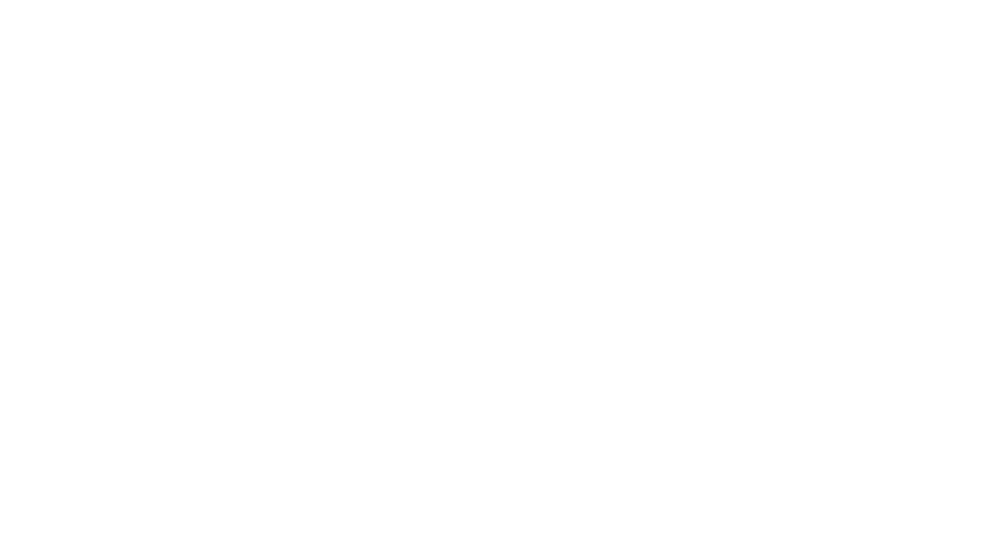人生は甘くはない。けど、捨てたものでもない。〜トルーマン・カポーティ『あるクリスマス』〜
『ティファニーで朝食を』『冷血』といった名作を生み出したトルーマン・カポーティの最晩年の作品に、『あるクリスマス』という短編がある。
クリスマスにちなんだ彼のもう一編『クリスマスの思い出』が、イノセントで心温まるストーリーなのに対し、『あるクリスマス』は、主要な人物を同じとしながらも、生きる哀しみ、孤独を相手取った、正反対の性格を持つ点で興味深い。

主人公は6歳になる男の子バディー。幼い頃に訳あって父母が離婚し、母方の親戚に身を寄せていた彼に、遠くニュー・オリンズに住む父親から、クリスマスに家に来ないか、との誘いを受ける。
バディーは泣いて嫌がる。なぜなら彼は、生まれてこのかた、アラバマの町を出たことがなかったばかりか、いとこであり大の親友でもあるスックという名の老女らに守られて生きてきたのだ。未知の世界に足を踏み入れ、ほとんど会ったこともない父親のもとで、わざわざクリスマスを過ごさなければならない理由は、彼になかった。
それでも「雪が見えるかもしれないから」とスックに促され、不安を胸にバスで旅立つ。ニュー・オリンズの父の家は豪華で、何もかも揃ってはいるけど、バディーの気持ちはぜんぜん落ち着かず、むしろ慣れない食事、街での振る舞い、そして父との生活に閉口ぎみだった。
そんなある日、足漕ぎ式の飛行機のおもちゃを店先で見つけたバディーは、その飛行機で大空を飛ぶイメージを膨らませ破顔一笑。その笑顔に、息子との距離を縮めたかった父親は、少しの自信を回復する。
バディーは、スックの言葉を信じ、サンタクロースにその飛行機を乞うたものの、クリスマス・イブに父親が必死にプレゼントを用意する場面を目撃しショックを受ける。バディーは父親からその飛行機をせしめ、アラバマへの帰路につこうとしていた時、酒の勢いを借りた父親に引き止められる。
「お前を帰したりしないぞ。あんな気の触れたボロ家の気の触れた連中の中にお前を帰すわけにはいかないんだ」。バディーの手首を強く掴み凄む父親は、「どうかキスをしておくれ。お願いだからキスをしておくれ。お父さんに愛しているって言ってくれ」と懇願する。バディーは、もはや瓦解寸前の父親を残し、そしてそれが、自分が帰ることを発端としていることを十分に理解しながら、おもちゃの飛行機を携えバスに乗る。
バディーはバスの中でひとり、幼心に苦悩を覚える。
「僕はこれまでに感じたことのないような痛みを感じた。体じゅうをその激しい痛みが刺した」
「その不思議な痛みは僕の体を去らなかった。ある意味では、その痛みはずっと今にいたるまで僕の体の中に残っている。そしてこれから先も去ることはないだろう」
アラバマの我が家で安息を得たバディーは、夢の中で“主”から告げられたことを、翌朝実行に移す。スックとともに郵便局に行き、父親に葉書を出したのだ。
「ぼくはいっしょうけんめいペダルをこぐれんしゅうをしているので、そのうちそらをとべるとおもう。だからそらをよくみていてね。あいしてます。バディー」
何年もの時を経て、父親が亡くなった際、その葉書は再びバディーの手元に戻る。父親は、貸し金庫の中でそれを大切にしまっていた、という事実が明かされ、この短い小説は終わる。
『あるクリスマス』は、決して離散した家族の悲惨な末路を示しているのではない。
人生に負い目を感じ続けた父にしろ、自らの野心と現実との狭間で身を滅ぼした母にしろ、そんな両親に傷つけられるだけ傷つけられたバディーにしろ、登場人物に明るい光はささない。にも関わらず、このストーリーからは、ある種の救いを感じることができる。
訳者である村上春樹は、あとがきでカポーティのことを「成長することの哀しみと痛みを終始描き続けた作家」と称している。
両親に捨てられたバディーは、幼くして大人になることを強要されつつ、スックや親戚たちに守られて生きてきたが、父親という、彼にとって異なる世界の住人との接触は、彼にもう一歩、大人の階段を登らせることとなった。
大人と子供 ─年齢の差を問わず、精神の在りようとして─ の最大の違いは、痛み、それも他者の痛みを、自分に引き寄せることができるかどうかにある。それをひとは、やさしさと言うのではないだろうか。
おもちゃの飛行機に自由を夢見たバディーは、自らの境遇から一生解放されることはなかったに違いない。そしてやはり、息子との生活を夢見た父親も、それを叶えることができなかった。でもきっと父親は、毎日のように空を見上げ、飛行機が飛んでくるのを心待ちにしていたはずである。バディーのあの葉書に、痛みを分かることができたものからの言葉に、父親がどれだけ救われたか。
小説のなかで特段の描写がなくても、カポーティが救われない終わりを用意していたとは思えない。この時期、彼自身も父親を亡くし、その痛みを感じ、救いを求めていたはずだから。
人生は甘くはない。けど、捨てたものでもない。
みなが浮き足立つクリスマスだからこそ読みたい、ほろ苦くもやさしさを感じる一冊だ。■bg