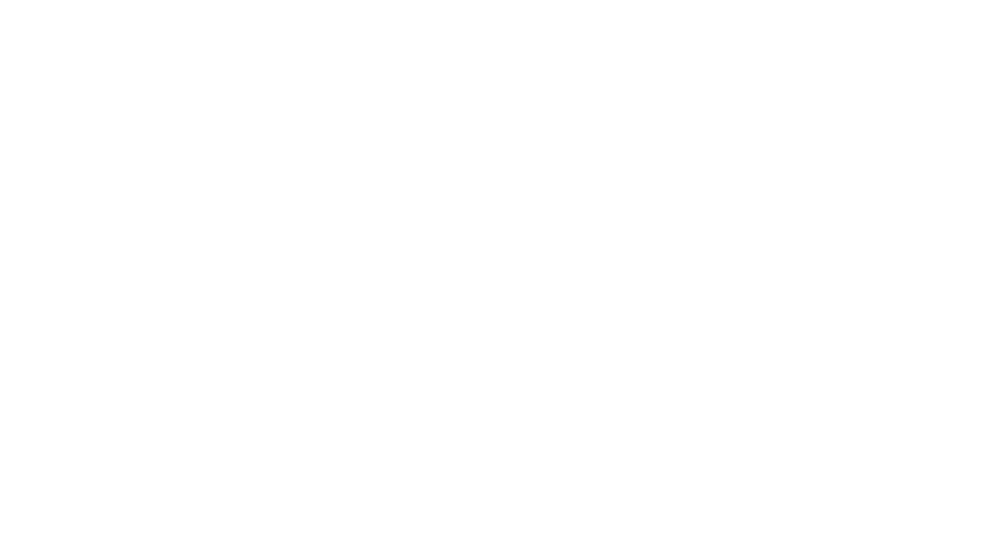「非共感的」な原発問題を超えて 〜 武田徹『私たちはこうして「原発大国」を選んだ』を読んで 〜
なぜ、反原発デモに通ったのか
2012年6月からおよそ半年の間、毎週金曜日に首相官邸前やその周辺で行われている反原発デモに足繁く通った。
最初に訪れたのが6月15日。ちょうどこの運動の規模が拡大を続け、徐々にメディアでも取り上げられるようになった時期と重なる。翌週22日には主催者発表で約4万5000人の参加者(警視庁発表で1万1000人)が発表され、「報道ステーション」でもレポートされはじめた。
そして6月29日、デモの熱気は最高潮に達し、15~18万人という威勢のいい数字が流れた。実際にはそんな法外な人数でもなかったが(警視庁調べでは約1万7000人)、官邸前の道路両脇の歩道に鈴なりになった群衆が一気に車道になだれ込み、危険性が高まったとして定時解散のデモが前倒しで終わる事態となった(以上、参加者の数字は津田大介『ウェブで政治を動かす!』参照)。

首相官邸前の反原発デモ(2012年6月29日撮影)。デモの熱気はこの日最高潮に達し、官邸前の車道に群衆がなだれ込む事態に発展した。
個人的には、原発をなくしたいというスタンスこそ周囲の人たちと同じだったかもしれないが、自分自身はデモに積極的に参加しているつもりはなかった。どちらかというと「いったいこの先、この運動はどうなるんだろうか?」という興味に突き動かされていた。
かつてこのエリアで繰り広げられたと聞く日米安保のデモは生まれる前の歴史上の出来事だが、目の前の反原発デモは現在進行形で展開されている。大袈裟にいえば、歴史の目撃者になるかもしれない、という予感もあった。
だがこの関心は、時間を経るに従って徐々に先細っていった。同時にデモの参加者は目にみえて減り、注目度も失われていった。
反原発デモの宿命
デモへの興味を失った理由は、主に2つあった。
ひとつは、あの反原発デモに潜在的にあったであろう課題に気がついたからだ。「再稼働反対!」「子供を守れ!」といった抗議の声をあげ続けることに意味がないとは決して思わない。ただ、目にみえるカタチで成果があらわれにくく、かつ組織動員にもよらなかったため、運動を持続させることが難しいという“宿命”があった。簡単に言えば、参加することに飽きてしまうのである。

殺伐とした雰囲気すら漂う反原発デモの会場にあって、田中康夫が配っていた「白い風船」は、場の空気を和ませる役割を担っていた。
おそらく運動はマンネリに陥り、拡大するどころか勢力も注目度も弱めてしまったのではないか。いまも毎週のように抗議は続いているというが、この反原発の運動が世論を巻き込んだ“うねり”となっているとはとても思えない。
成果があらわれにくいのなら、デモを主催する上での工夫があってもよかった。最終的に脱原発を目標とするなら、それまでのマイルストーンを設定し、運動の進捗を確認しあえるような考えもあっただろう。また、声を上げるだけというスタイルとは別に、勉強会でも、あるいは著名人を巻き込んでのイベントなどもあってよかった。ひとつではない、何か別のアプローチは、きっとあったはずである。
実際、時の民主党政権は「原発ゼロ社会」に舵を切ろうとしていたわけで、大飯原発は再稼働となったが、運動の成果は出ていたとみることもできる。再稼働を堂々と宣言している自民党とはずいぶんと対照的ではないか。
「解決」ではなく「対決」の姿勢
目的を達成するまでの戦略やプランが一向にみえてこなかったこと。これがこの運動への興味を失ったもうひとつの理由である。
このデモに限ったことではないが、原発に反対する勢力は(デモ主催者のみならず、脱あるいは卒原発を訴える政治家・政党までもが)、少しでも原発を肯定的に捉える(ようにみえる)あらゆる政策、思想、行動に、何が何でも反対する。東電、政府、官僚、御用学者、マスゴミという“敵軍”の跋扈に必死に抗う正義の市民たち ── そういった枠に自らをはめ込み、「解決」ではなく「対決」を求めているかのようにみえる姿勢に、いつしか疑問を感じるようになった。

反原発デモは国会議事堂前にもエリアを拡大。主催者により子連れでの参加者向けスペースも設置された。
「原発をどうやって止めるか」という命題に対する、具体的な取り組みをまとめるのは容易ではない。稼働を止めたところで消えない大量の放射性物質・廃棄物の処分方法をとってみても、国内外の専門家から意見を聞き、議論を尽くしに尽くし、それでも万人が満足するような結論が出るとは限らない。複雑怪奇な原発というテーマに、「とりあえず何でもノーで突き通す」という子供じみた態度でのぞむのは無謀というもので、このままでは渇望する脱原発はとても実現しないだろう、と思うようになったのだ。
デモが一部の特殊なグループによるものだった時代が終わり、誰もが気軽に参加できるようになったのは大きな進歩だった。しかし、デモだけでも、全面的に反対することでも、原発社会から脱することはできないのではないか。
再稼働への準備が粛々と進められているかにみえる日本。3.11、そして福島の原発事故は、天災と人災があわさった未曾有の大惨事だったが、一方で、この国が歩んできた道と、今後進むべき方向を考える上では好機でもあったはずである。
だが私たちの社会は、またかつてのやり方、生き方に“何となく”戻りはじめているように思えてならない。“かつての生き方”はもう長くは続けられないだろう、という淡い不安と密かな確信を抱きながら。
スイシン対ハンタイという二項対立を超えようとする一冊
閉塞感漂う原発問題にどうやって突破口を見出すのか。より建設的で前向きな議論はできないものか。膠着状態を打開したいという想いが伝わってくる一冊が、『私たちはこうして「原発大国」を選んだ』である。

本書は2006年に刊行された『「核論」── 鉄腕アトムと原発事故のあいだ』をベースに、2011年3月の福島原発事故を受けて若干加筆・修正されたもので、日本と原子力の関わりを時系列的な章立てで検証するという構成を取っている。著者はメディアやジャーナリズムに明るい論客、恵泉女学園大学教授でもある武田徹だ。
この本の最大の特徴は、原発「スイシン派」にも「ハンタイ派」にも寄らない書き手の姿勢が終始貫かれていること。一方的に危機意識を煽る巷の原発本とは一線を画している。それゆえにハッキリした結論なり分かりやすい道筋を求める向きには、スイシン・ハンタイの立場に関わらず「煮え切らない」読後感を与えるのではないだろうか。
しかし、だからといって内容に物足りなさを感じることはない。日本における原子力の黎明期から、いかに原発が豊かさの陰で社会にとけ込んでいったかを追うには最適な一冊である。そして「どちらにも寄らない」という中庸な立ち位置は、スイシン派にもハンタイ派にも通じる、問題解決への糸口となるかもしれない、そんな予感を抱かせてくれる。
原発大国へと突き進んでいく日本の足跡
話は日本における原子力の夜明けからはじまる。
敗戦直後、世界で初めて原爆が兵器として使われて間もない1946年、旧体制下への未練を断ち切れないでいた日本の憲法起草委員に、占領国アメリカが突きつけた「戦争の永久放棄」「国民主権、象徴天皇」そして「貴族廃止、皇室財産の国家帰属」。これらを踏襲した新憲法の誕生と、その後の日本の高度経済成長の背景には、どの国よりも早く核と原子力の技術を確立したアメリカの影響があった。
やがて他国が次々と核兵器を手に入れる一方で武器としての核を持てない日本は、しかしアメリカの核の傘の下という安全保障の枠組みのなかで、原子力の平和利用としての原子力発電で核のポテンシャルを保持するまでになる。そういった複雑な構造は、経済的な豊かさのなかでいつしか忘れ去られ、日本は原発大国へと突き進んでいく。
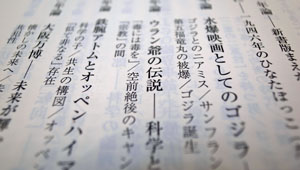
この「はじめに ─ 一九四六年のひなたぼっこ(ただし原子力的日光の中での)」を前口上に、中曽根康弘代議士が日本で初めて原子力予算を国会に通した「一九五四年論」や、科学の子・鉄腕アトムと原子爆弾を開発したオッペンハイマーの運命をなぞる「一九六五年論」、国をあげて科学に熱狂した大阪万博の意味を問う「一九七〇年論」、原発と立地する過疎地、都市との関係性を検証する「一九七四年論」、記憶に新しいJCO臨界事故の悲劇には原発ハンタイ派も無縁ではなかったとする「一九九九年論」など、福島原発後に書き加えられた「二〇一一年論」を含め全10章で構成されている。
この本では、日本が50数基もの原発を抱えるに至った足跡が、最適と思われる情報の幅、奥行きでまとめられている。戦後史のなかで核や原子力が、科学、思想、文化、社会の面でどのような議論を起こし、また社会に受け入れられ、拒絶されてきたか。読み進めれば、「原子力的日光の中」にあった日本という国の実像が浮かび上がってくる。
スイシン、ハンタイにも「非共感的」な立場
本書の締めくくり「おわりに」のなかで、武田は科学技術史を専門とする吉岡斉の『原子力の社会史』から、「非共感的」という言葉を引いている。
「非共感的」とは、電力業界に対して、あらかじめ敵対するわけではないが、批判的な立場を取るということ。日本の原子力の取り組みを全否定はしないが、特にスイシン広報など共感できない部分があるということを意味している。
武田はこれに「反核運動家、反原発運動家」をも加えて「共感できない」としている。原発に反対する運動は「科学的な思考を手放すリリースポイントが早すぎる」(272ページ)からという理由だ。
放射能や核を過剰に恐怖するあまり、体系的知識であるはずの科学に早々に見切りをつけてしまう傾向は、個人的にも日頃ツイッターやブログを眺め、原発や放射能を問題とする人たちの言動から感じていたことでもあった(現に自分も、ちょっと前までその傾向にどっぷり浸かっていたという実感もある)。
ここまでで終わると、単なる「福島第一原発事故による健康被害を恐れるあまり、事実を曲解・誇張して放射能の脅威を主張する人々を指す呼称」としての“放射脳”な人々への批判に取られかねないが、武田はさらに「核」はそもそも正当に理解できるものなのか、と問いかける。

「一九五四年論 ウラン爺の伝説」では、“健康にいい”とウラン鉱を風呂や畑に入れた、かつての放射能フィーバーなどについて触れ、放射能を受け入れるのにも拒絶するにも、人々に宗教的な“信仰”に近い心理状態が生まれる背景について論じられている。いわゆる「放射脳」と呼ばれる人たちの傾向と照らし合わせて読むと興味深い。
量子論という先端の科学抜きに放射能や核を語ることはできない。地球全体を巻き込む巨大な「核」エネルギーは、「最小」から「最大」という広大な領域に影響が及び、捉え所がない(素人ならなおさら)。さらに物理現象のみならず、「核」を巡る歴史的な背景、被爆国という日本固有の史実が加わり、「核」は理解しようにも理解しづらいものになっている。
原発事故以降よく聞かれるようになった、寺田寅彦の「ものを怖がらなさ過ぎたり、怖がり過ぎたりするのはやさしいが、正当に怖がることは、なかなかむつかしい」という言葉があるが、武田は「そんな『核』の在りようを的確に見定めることは困難であり、だから正当に怖がることがなかなか出来ない。」(274ページ)と記すのである。
しかし、「正当に怖がる」ことを諦めるわけではなく、だからこそ「正当に怖がるために」、様々なレイヤーが折り重なる核や原子力について、スイシンにもハンタイにも属さない立場で丁寧に調べ、論じようとしているのである。
「なぜ」に対する答えの探求
21世紀の日本に暮らす我々にとって、戦中戦後に先人が味わった苦難を想像することは容易くない。先の大戦を資源戦争だとすれば、近代化を目指すなかでいかに資源が枯渇し、それを渇望していたかは、歴史を丁寧に紐解かないとなかなか分からないだろう。
戦後復興の第一歩を踏み出すにあたり、国を動かす原動力としての資源、エネルギー問題は避けて通れなかったはずである。そこに占領国アメリカから示された原子力発電という可能性は、敗戦国日本にとって新たな国家基盤を形成するための「夢の技術」であったのだろう。そうでなければ、被爆国という暗く重い歴史を背負うことになった日本が、平和利用の名のもととはいえ、原発を50基以上も保有するに至った経緯がうまく説明できない。
一方で、原子力発電という平和利用の陰には、安全保障における「核の抑止力」という効果も認められていただろう。国を画するという意味において国防を無視するわけにはいかない。平和憲法という国家の原則と日米同盟のなかで、原子力が持つ軍事的なポテンシャルを利用したいとする考えも、また一定の理解が及ぶ領域にある(それに納得するかは別問題だ)。
なぜ、極東の島国、地震国日本にこれだけの原発が造られたのか?
なぜ、多くの国民は原発の存在を知っていながらそれを生活の一部として取り入れてきたのか?
なぜ、原発は都市ではなく過疎地に立地しているのか?
なぜ、核や放射能は人々を混乱させ、また時に熱狂させるのか?
なぜ、スイシン派とハンタイ派は反目を続けるのか?
すべてに明快な解があるほど事は簡単ではないが、そういったひとつひとつの「なぜ」に対する答えを探求する姿勢こそ、3.11以降の日本に求められているものではないだろうか。
「子供を守ること」とは何なのか?
先の反原発デモでよく聞かれるフレーズに「子供を守れ!」というものがあった。
私にも3歳になる息子がおり、彼がこれから生きていく社会に対する責任というものを感じずにはいられないでいる。ひょっとすると彼がいなければ、原発にしろ、この国の将来にしろ、今のような意識を持つことはなかったかもしれない。
放射能は怖い。
自分はもちろん、息子にもその影響が及ぶことは何としても避けたい。
その根源たる原発を、決して快くは思っていない。
なくしてしまいたいという想いもある。
ただ、あの「子供を守れ!」というメッセージには、どこかで「非共感的」にならざるを得ないのである。
本当に大切なのは「子供を守ること」なのか?
子供たちから、原発や核や放射能汚染を遠ざけることが目的なのか?
その方法を、どれほどまでに考え、また議論しているのか?
3.11の時、息子は10ヵ月だった。
地震、津波、原発事故、天災に人災、あの大惨事がどれほど酷いものだったか。また震災直後に福島はいわきにいる義母や義姉・妹家族、総勢11人が東京の我が家に避難してきたことなどは、おそらく彼の記憶には残っていないだろう。
彼がこの先、物事の判断がつくようになり、何かを考える力が育っていくなかで、父として、あの出来事をどう伝えるか。
私の親としての宿題は、子供を守るためにどのような道があるのかを考えること、国や社会という大きな枠組みを通時的に捉え、歴史を学び、その在り方を検証していくこと。その行き着く先に、子供たちにとっての、少なくとも今よりはマシな社会があるのではないか。
人は何かと共感を求めたがる動物であり、気がつけば共感できる=自分に都合のいい情報だけに接しているものだ。
チェルノブイリの健康被害を調べた誰々博士、原子力の利権構造を暴く誰々ジャーナリストや何とか新聞、そういった情報源の偏在は、社会からしなやかさを奪い、硬直化を促す。そして原発を「絶対悪」としかみない視座、それを廃することが「疑いようのない正義」という信念、そうした極度に単純化した対立の温床となる。しかし世の中がそんなシンプルな要素でできているわけではない、ということは、社会生活を日々送っている人なら気がついているはずである。
『私たちはこうして「原発大国」を選んだ』は、我々の社会に厳然とある原発という問題への、思考と検証のガイドのようなものだ。そこ書かれていることすべてに理解を示し、納得する必要はない。ただ、知るべき情報や、自分とは異なった考えに触れることは、決して無益にはならないはずである。■ bg
『私たちはこうして「原発大国」を選んだ』
武田徹 著
中公新書ラクレ
定価(本体840円+税)