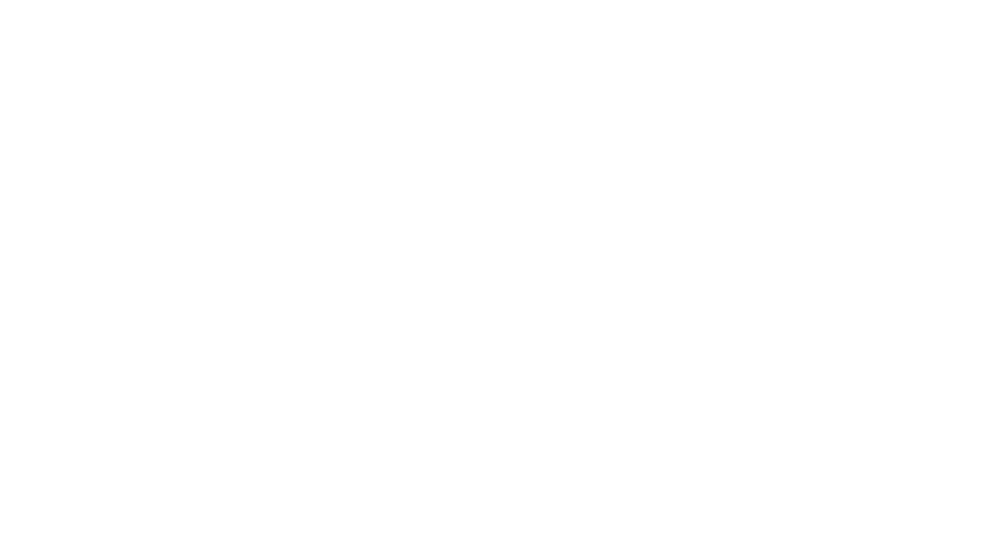「何かを理解したかのような気分」という病 ~ 蓮實重彦『齟齬の誘惑』を再読して ~
東大生が理解できなかった、東大入学式での東大総長の式辞
この本を最初に読んだのは発売後間もない2000年頃だったか。「東大生が理解できなかった、東大入学式での東大総長の式辞」という当時の評判に“非東大生”が触発されたわけである。
当時20代半ばの自分がどれほどまで内容を理解していたかはあやしいところだが、少なくとも40歳になった今になってふと読み返したくなったのだから、何かしらの“意識の欠片”が残っていたのだろう。
実際、再び『齟齬の誘惑』のページをめくると、あの頃ぼんやりとしていたこの本の輪郭が、ぐっとはっきり見えたような気がするのだった。そして、これは今こそ再読すべき本だった、と確信したのだった。
「何かを理解する」と 「何かを理解したかのような気分」の違い
『齟齬の誘惑』には、1997年から2001年まで東京大学総長を務めた蓮實重彦による、初期の講演や挨拶が集録されている。なかでも序章の「齟齬感と違和感と隔たりの意識」は、1999年4月12日に日本武道館で行われた入学式の式辞を書き起したもので、その晦渋な内容に出席者が困惑したという有名なエピソードは冒頭で紹介した通りだ。

この難解に読める式辞の前に、「いま、この書物の読者となろうとしているあたなに」という前口上で、手がかりをしっかりと掴んでおきたい。
そこには、「何かを理解すること」と「何かを理解したかのような気分」になることには、超えがたい距離が拡がっている、とある。
しかし人々は往々にして「何かを理解したかのような気分」で、「何かを理解したこと」と同じように振るまいがちであると続く。
「何かを理解する」と「何かを理解したかのような気分」の違いとは何か。
「気分」とは、一定期間持続する漠然とした心身の状態のことを指す。
分かった気になると書いて「気分」だ。
「気分」のなかにあれば、何かについて詳細に調べたり、厳密に定義したり、議論を戦わせることが必要とされない。
その気になっていればOKなのだから。
また「気分」である以上、何らかの問題の解決を主体的に行うことはない。
なんとなく分かった状態の人間が、具体的で有効な解決策を打ち出せるはずもない。
そして、問題自体も自分のものとして考えることができない。
多分に当事者意識が薄い状態で流れに身を任せていればいい。
そしてそれが「気分」であれば、“これは問題だ”にしろ、“いや問題はない”にしろ、どちらも大した違いはない。
腐るほど情報が転がっている世の中で生きている忙しい現代人が、「気分」に流され埋もれてしまうことは仕方がないかもしれない。しかし、蓮實はそれにノーを叩き付ける。
何故なら、この「何かを理解したかのような気分」の蔓延は、「知性」にとって由々しき事態であるからだ。
「知性」を率先して実践する場としての大学
齟齬とは、物事がうまく噛み合わないこと、食い違うということである。
噛み合わないことの誘惑とは、いったい何を意味するのか。
式辞の冒頭、蓮實は、入学式のような儀式は「退屈さの同義語」でも「通過儀礼の一つとして、とりあえずは耐えておくべき無駄な時間」でもなく、本来そこでは「共感とは異質のある種の齟齬感が、同調からくる納得ではにわかに処理しかねる違和感が、あるいは、親密さではなく、むしろそれをこばんでいるかにみえる隔たりの意識が、意味の生成に深くかかわるものとして浮上してまいります」と語る。
そして「実際、社会とは、いくつもの齟齬感や、違和感や、隔たりの意識が複雑に交錯しあう過酷な空間にほかなりません」(以上、6ページ)と続けるのである。
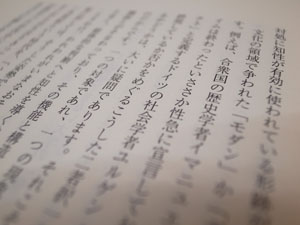
齟齬感や、違和感や、隔たりの意識が複雑に交錯しあう過酷な空間の一例として、「国際化」を挙げる。
「国際的な相互理解」などという美辞麗句は、たんなる観念に過ぎない。
「実際、具体的な国際性とは、野蛮と呼ぶほかはない不幸な推移を示している現在のコソボ情勢がそうであるように、無数の差異がまがまがしく顕在化される過酷な空間にほかなりません」(9ページ)。当時泥沼化していたバルカン半島での武力衝突のみならず、今なお続く国と国、地域と地域、民族と民族の争いを前に、相互理解という言葉やコミュニケーション能力だけでは問題の解決など到底に無理だということは明白だろう。
何故争うのか。どうして憎しみあわなければならないのか。
そういった齟齬感や違和感を前にすると、ひとは戸惑い、苛立ちを覚える。
だがその苛立ちを遠ざけるのではなく、むしろ「率直な驚きとともにその不自然さを受け入れようとする」(7ページ)資質こそが、年齢に関係のない「若さ」というものだと蓮實は説く。
過酷な空間のなかでも、異なるものを前にして拒絶することなく、好奇心を抱きながら、対象の何たるやを自分に引き寄せ、考える。
すなわち、それが「若さ」であり、「知性」であり、「知性」を率先して実践する場こそが大学である。
総長として、またアカデミズムに携わるものとして、蓮實の主張の柱はそこにある。
歴史の出来事として片づけるのか、違和感や齟齬感を覚えながら意味を問えるのか

さらに総長は、明治10年(1877年)4月12日、東京開成学校と東京医学校が合併し誕生した東京大学を例に挙げ、「はたしてその時代を、具体的なイメージとして想像しつつ、自分の生きた体験とすることができるでしょうか」(10ページ)と学生たちに問いかける。
122年前といえば、西南戦争で西郷隆盛が戦火を交えている最中であり、日本は議会制度はおろか憲法すら持たない状態だった。10歳の夏目漱石は文字通りの“坊ちゃんで”、ゴッホはあの名作『ひまわり』すら描き上げておらず、『資本論』はまだ第2巻が日の目を見ていない。『変身』のカフカは誕生すらしておらず、フッサールの現象学も、ソシュールの一般言語学も、フロイトの精神分析学も、さらにはアインシュタインの相対性理論も、今では常識的に語られる様々な理論が生まれていなかった時代である。
そういった事実を、たんに歴史の出来事として片づけるのか、違和感や齟齬感を覚えながらその意味を問えるのか。「知性」とは、物事に遭遇した最初の心持ち次第で芽吹くかどうかが分かれる。
性急に答えを求めてはいないか
この本を再読してあらためて考えたのは、このご時世に我々、というか、そもそも自分自身が「齟齬」とどう向き合っているのかということだった。
「何かを理解したかのような気分」という病に罹っていないか?
何かに対し、性急に答えを求めてはいないか?
世界には、ひとりの人間では到底知り得ないことがあり、多種多様な考えや信念やひとびとの生活がある。
そんな「世界」を知ったつもりになってはいないか?
年を取れば、多少は経験も知識も身に付くもの。
自分が不惑の年齢を迎え、ささやかでも慢心と思しき姿勢の兆候を覚えた時、この本のことをふと思い出した。
誰よりも今の自分に投げかけたい問いかけが詰まっていた。
齟齬や違和感から目をそらしてはいけない。
たんなる「気分」に終わらせてはいけない。
若い頃、「分かった気分」で終わっていた自分だったけど、そういった背伸びも無意味とはいえないものだということに、十数年経って気がついた。■ bg
『齟齬の誘惑』
蓮實重彦 著
東京大学出版会