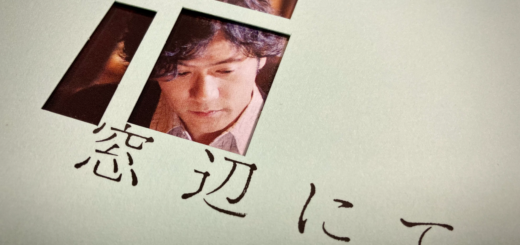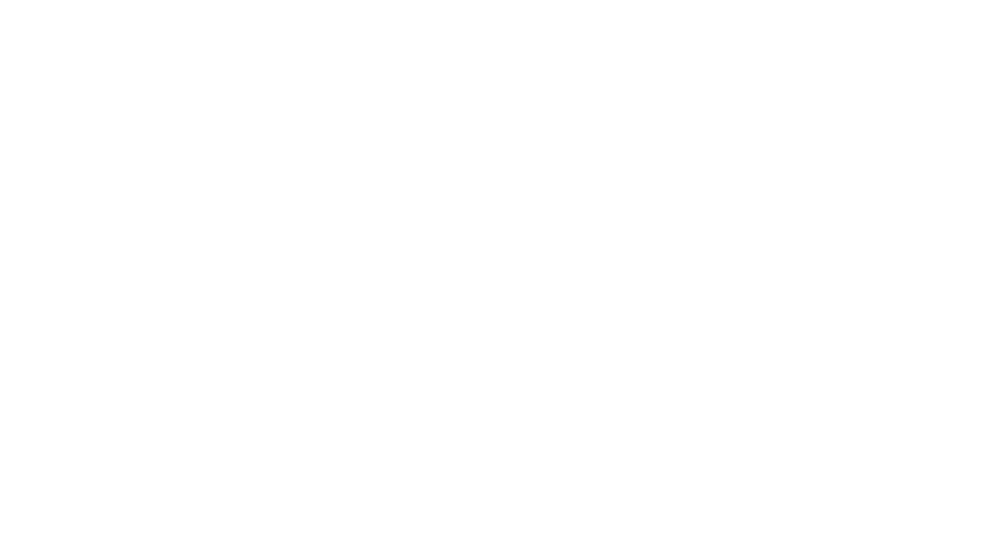科学とは、信仰とは何か〜新国立劇場『骨と十字架』観劇〜
新国立劇場で『骨と十字架』を観劇したのは2019年7月のこと。劇団「パラドックス定数」の野木萌葱による史実と虚構を織り交ぜたストーリーを、新国立劇場芸術監督である小川絵梨子が演出した、同劇場2018/2019シーズンの掉尾を飾る舞台劇だった。

新国立劇場『骨と十字架』
聖職者にして古生物学者、実在した司祭を巡る騒動
『骨と十字架』の登場人物は、実在したフランス人司祭であるピエール・テイヤール・ド・シャルダン(1881年 – 1955年)をはじめ5人すべてが聖職者。それぞれイエズス会や、宗教裁判を司る検邪聖省と立場は違えど、みなキリストの教えに従う点では共通している。しかし、異端ぶりを発揮するテイヤールを巡っては、各人が異なる意見や思惑を抱きながら話は進行していく。
司祭でありながら地質学者、そして古生物学者だった神農直隆演じるテイヤールは、自身が著した論文が火種となり、イエズス会から問題視される。「最初の人間はアダム」と信じるキリスト教とは真っ向から対立する、サルからヒトへの「進化論」を支持していたテイヤールは危険分子とみなされ、ヨーロッパから遠い北京への赴任を命じられてしまう。
だが当のテイヤールは、教義と自らの主張に矛盾は感じていなかった。「聖書は事実の比喩」という持論を展開し、聖職者を続けながら学問を深めることは可能であるとの立場を怯まずに貫き通す。北京では、同じ宣教師で学者のエミール・リサン(伊達暁)とともに化石の発掘調査を続け、そして人類の進化の過程を示す証拠、北京原人の化石発掘という大発見に立ち会う。本作のタイトルは、この世紀の発見に由来する。
舞台の前後半で起こる立場の逆転
この舞台の眼目は、前半と後半とでテイヤールをはじめとする人物の立場が大きく変わるところにある。
前半は、純真無垢なまでの信念を押し通すテイヤールと、教義に反する彼を追放しようとする宗教警察たる検邪聖省の対立を軸として進む。自明となりつつある進化論を、キリスト教を維持し支えんとする「組織の論理」が拒んでいるという構造としてみると、真実を追い求めるテイヤールに肩入れし、また検邪聖省への反抗心すら芽生えてくるかもしれない。
これが後半になると形勢が一変。北京原人の化石を発掘したテイヤールが、「この発見が神の否定になりかねない」ことに(ようやく)気がつき、それまでのみなぎるような自信が失せ、この先の身の振り方を見失ってしまう。路頭に迷うテイヤールに救いの手を差し伸べたのは、意外にもこれまで敵対していた検邪聖省のレジナルド・ガリグー・ラグランジェ(近藤芳正)だった。
テイヤールと“原爆の父”
検邪聖省や総本山ヴァチカンがテイヤールを危険とした理由は、キリスト教の教義に反するからだったかもしれないが、観ているものとしては別の点で彼はかなり“危険”だった。
「神は手の届かない、天高い場所におられる」という、ごく一般的な“天の神様的イメージ”に対し、テイヤールの口から語られたのは、「何万年もの進化を重ねて、ヒトは必ず神に辿り着きます」と、まるで神が到達可能な存在であるかのような答えだった。研鑽を積み真理を追究することで、創造主の神がカタチづくった世界を知る、という意味の比喩だろうが、しかしそのナイーブな姿勢にこそ、テイヤールのみならず科学全般に潜む危うさがある。
観劇中にふと頭を過ぎったのが、ロバート・オッペンハイマー(1904年 – 1967年)のことだった。カリフォルニアの大学で物理学の教鞭を執っていたオッペンハイマーは、第二次世界大戦の最中に国家的な策略「マンハッタン計画」に加担することで、後に“原爆の父”として知られることになる人物である。
ナチス・ドイツの原子爆弾開発に対抗することを目的に、アメリカを中心に優秀な科学者や技術者を総動員して立ち上げられたマンハッタン計画。オッペンハイマーは、科学部門のリーダーとしてこの巨大プロジェクトを主導、難題を次々とクリアしながら、人類初の核実験「トリニティ」を成功させる。彼らが手がけた原爆は、アメリカ陸空軍の爆撃機に搭載され、日本の広島・長崎に投下、大戦は終結した。
原爆製造を後押しし、実戦投入に踏み切る決断を下したのは「政治」、その原爆製造に欠かせなかったのが「科学」だった。後日、ナチスの原爆開発は心配に値するほどの成果を出しておらず、アメリカを含む連合国軍側の勇み足でしかなかったことが判明。核という人類史上稀に見る強力な武器を手に入れたアメリカと、少し遅れて核を手にするソ連との間に、冷戦という政治問題が新たに立ち現れることになる。
その後、原爆開発に携わった科学者たちは複雑な思いを抱いていた。なかでもオッペンハイマーは核兵器に反対するようになり、人智を超えた破壊力を生み出したことに、古代インドの聖典の一節「I am become Death, the destroyer of worlds.(我は死神、世界の破壊者なり)」を引き、後悔と懺悔の念を語っている。
オッペンハイマーだけではない。時のアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトに原爆開発を進言する手紙を書いたのは、かのアルベルト・アインシュタイン。ウランによる連鎖反応が強力な爆弾となる可能性を示唆し、政府に開発支援を要請する内容の書簡を送ったことに天才物理学者は心底後悔していたとされ、後に「ラッセル=アインシュタイン宣言」として核兵器廃絶を訴えるに至る。
信仰が宿るところ
テイヤールとオッペンハイマー。それぞれ立場も志も異なるが、自然界の出来事を探求するという自ら信じた道を邁進した果てに、落とし穴にすっぽりと落ちてしまった点は同じである。劇中のテイヤールに、あるいはオッペンハイマーを含め彼らに欠けていたのは、科学はあくまでも「手段」であって「目的」ではないという視点ではなかったのかと思う。
ヒトがアダムからではなくサルから進化していったとする進化論は、ヒトにより発見されたが、ヒトにより引き起こされたわけではない。仮にその進化が神の手によるものだとしても、ヒトは進化のプロセスの只中にいるだけで、行き着く先の状況に対してヒトが責任を負えるはずはない。
オッペンハイマーも同様に、原爆を可能とする方法を見つけただけで、その後の核兵器による人類滅亡の脅威を前にして彼は無力だった。ヒトが科学的事象に責任をもって対応できるとは限らないのだから、科学を「目的」としてしまった場合、予想もしなかった事態に陥ることは多々あることだろう。
科学を「手段」にとどめるならば、「目的」は、多くにとっての「救い」であってほしい。その意味で『骨と十字架』の最後のシーンには、そのヒントが隠されていた。
神の否定の可能性という真実に慄き、道に迷いはじめたテイヤールに手を差し伸べたのは、かつて敵対していたラグランジェ。迷いや孤独から人を救うという、宗教の大きな役割を思い出させたところで劇の幕は降りる。心の救いは、いくら科学が発達しても、またいつの時代になっても必要とされるもの。信仰とは教義云々ではなく、救おうとする気持ちにこそ宿るものという、極めてシンプルな解を用意してくれていたように思う。■bg