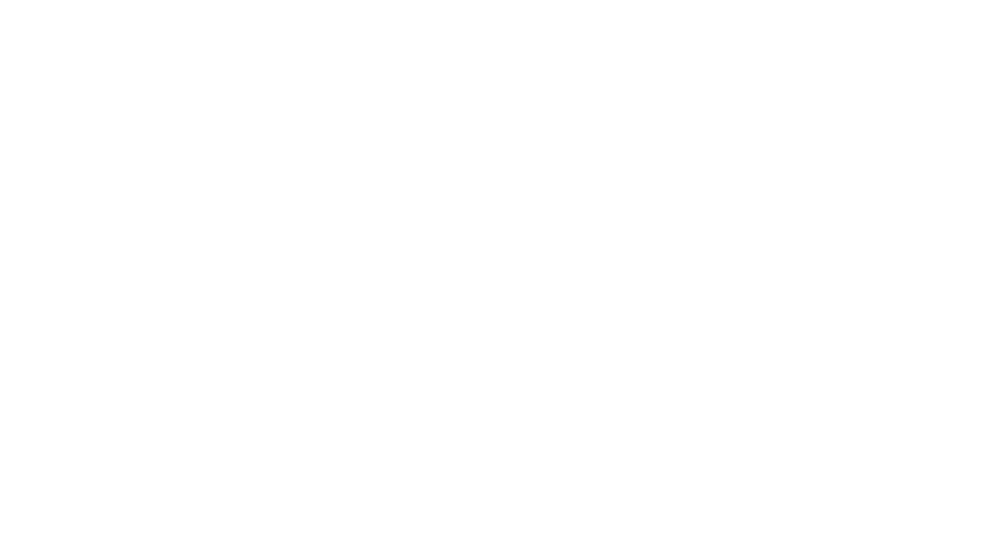第2章:都の西限、双子の明暗 ~ 横田基地と立川基地~その4「基地問題を本土から消し去る」
立川基地と横田基地、東京の2つの基地の歴史を振り返ってみると、今回のテーマである「死角と構造」を、随所に、多層的に見つけることができる。この章の最後では、その死角と構造を「支えるもの」についても考えてみたい。
「巨大なサークル」で守られた首都圏
立川基地と横田基地の歴史から紐解く「死角と構造」とは何か。
まずは「基地の不可視化」、基地機能を東京の奥地へと「押し込めた」ことによる巨大な枠組みである。
その2「基地の街から中核都市へ ── 立川の転身」で触れた通り、第一次世界大戦(1914〜1918年)直後の1922年(大正11年)、帝都防衛のために立川基地(立川飛行場)が造られた。この場所が選ばれた理由は、アクセスに優れた立川駅の近傍に、飛行場建設に適した広大かつ容易に接収できる土地があったという、立地条件の良さからだった。
立川基地誕生から18年、弟分の多摩陸軍飛行場すなわち横田基地ができる。当初は立川が「主」であり、数km離れた横田は立川を補完する付属施設であったというが、歳は離れているとはいえ、その実は首都の空を守る砦という意味で、両者は双子のようなものだった。
この兄弟の立場が逆転したのは、戦後アメリカの基地として使われるようになってから。1950年(昭和25年)に勃発した朝鮮戦争を機に、アメリカの反共政策に後押しされるかたちで日本の軍備増強が進むと、「軍都」立川では基地拡張反対の声が大きくなり、砂川闘争へと発展。こうした反基地運動が、安全保障上の同盟関係を維持することで相通じる日米両政府の頭痛の種となっていった。
やがて日米の思惑が一致し「関東計画」が決定。都市に近く人口も多い立川を諦めるかわり、他の首都圏の米軍施設を含め横田に軍事機能を集約し、基地や軍事施設を多くの人間から「不可視」にしてしまった。
東京における基地の変遷をごくごく簡単にまとめればこうなる。
その流れを頭に置きながら、あらためて東京近郊の地図に目をやると、あることに気がつくだろう。
その1「国道16号線のアメリカ」で書いた、横田基地沿いの国道16号線は、「東京環状」という通称が示すように、都心部から半径30〜40kmの距離で東京圏をぐるりと囲むように走っている。
横田基地をはじめ、神奈川にある厚木基地や横須賀基地といった米軍基地、さらには埼玉の入間基地、千葉の木更津駐屯地といった自衛隊施設は、国道16号線周辺に位置していることが分かる。
国道16号線という「巨大なサークル」で、首都圏の人口密集地が守られているかのようにも見える。基地が「死角」に置かれ、基地問題自体を目立たないようにする「構造」が、ここにあっさりと可視化される。
都の西に隠された、本土最大の米空軍基地
何故、横田が首都・東京の米軍基地として残されたのか。最大の理由はそのロケーションにある。
立川に基地(飛行場)ができた理由のひとつに「土地が平坦で広大なこと」という条件があったが、立川の西にある横田のさらに西からは、いよいよ関東山地がはじまってしまう。ここは都(みやこ)に置ける基地としては一番西の端っこにあたるといっていい。都下の中核都市になった立川の陰に、本土最大の米空軍基地が隠されているのだ。
一方、横田基地自体にも「問題を外に追いやる力」が働いている。1971年(昭和46年)に戦闘機部隊が横田から沖縄の嘉手納基地に移動。いまもなお横田周辺に真の意味での静寂は戻ってきてはいないが、およそ1600kmも離れた場所に厄介なものをひとつ「寄せる」ことで、基地周辺のみならず、東京に住む私たちにも恩恵がもたらされた。
そして横田の周辺自治体には交付金を投入し、基地を抱えることで生じる様々な不都合への手当を行った。
反対運動へと突き動かしたものとは
東京をはじめとする首都圏における基地の「不可視化」は、日米両国を推進役とした関東計画で一応の完了を見たといえるが、この巨大な構造の形成に政府「だけ」が関わったと言い切れるものでもない。
民意 ━━ あるいはもっと情緒的な国民感情 ━━ が対をなしていたはずである。
立川基地返還に弾みをつけた砂川闘争をはじめ、1950年代には石川県の内灘闘争(1953年〜)、群馬県から長野県にかけての浅間・妙義山闘争(1954年〜)と、全国各地で軍事施設を巡る反対運動が勢いづいていた。
これら反対を訴える人々を運動へと突き動かしたものは何だったのか。
騒音や事故など諸悪の根源となる軍事施設は御免だ、というNIMBY(Not In My Back Yard/必要性は認めるが自らの居住地にはつくらないでくれ)精神の発露だといえばそれまでだが、時計の針を70年余戻した上で、彼らの心情を推し量る必要がある。
基地反対運動の潮流は、大別すると2つあるように見える。
ひとつは1950年代に起こった砂川や内灘、浅間・妙義山の各闘争に代表される、戦争終結直後の、「かつての敵国」であり「戦勝国かつ占領国」アメリカへの反発を基底としているもの。
もうひとつは1960年代以降、国土が復興を遂げ豊かな社会がかたちづくられていくなかでの、平和運動的な意味合いを濃くした反米・反基地運動である。
■「生活権を守る」戦い
まずは1950年代の反対運動は「生活権を守る」ことに軸足を置く戦いだった。
ほんの数年前まで殺し合いを繰り広げたアメリカが、戦勝国として敗戦国である日本を占領する、という状況は、現在のような(一応の)対等を謳う日米関係に慣れた今人となっては想像しづらいかもしれない。自分たちのコミュニティに入り込んでくるのはただの軍事施設ではない。「戦争に勝ったよその国」アメリカの軍隊である。それまで日本人が経験したことのない事態に、市井の臣が嫌悪や恐れを抱くことは想像に難くない。
そんな当時の状況を推察する手がかりを、たびたび引き合いに出す『基地はなぜ沖縄に集中しているのか』(NHK取材班著)に見つけることができる。
アメリカの海兵隊(Marine Corps)といえば、海外での武力行使を前提とした部隊であり、アメリカ国外に司令部を置く世界唯一の海兵遠征軍は沖縄に置かれている。
この在沖海兵隊、第二次世界大戦末期に沖縄で激しい戦闘を繰り広げた部隊が、戦後も引き続き駐留しているわけではない。
終戦直後の沖縄で占領政策にあたったのは米陸軍・空軍の部隊で、海兵隊のほとんどは日本本土に移った後、程なくしてアメリカへ帰国し解散している。この精鋭部隊が再び極東の島国に派兵されたのは1953年(昭和28年)。朝鮮戦争の長期化に伴い、戦略予備軍として第三海兵師団が日本に派遣された。
その行き先は、沖縄ではなく日本本土。キャンプ岐阜とキャンプ富士(山梨県)に司令部が置かれ、神奈川県横須賀市や兵庫県神戸市など全国各所に部隊が散らばっていった
(『基地はなぜ沖縄に集中しているのか』NHK取材班著 22〜23ページ)。

『基地はなぜ沖縄に集中しているのか』(NHK取材班著)によると、終戦直後、アメリカの海兵隊員と一般市民は隣り合わせで生活していたという。(撮影=bg)
こうした本土の海兵隊員らは、日本の一般市民に混じって普通の生活を営みながら訓練に精を出していた。海兵隊の兵士と一般人が一緒に電車に乗っている様子が『基地はなぜ〜』では写真入りで紹介されている。
米軍の「近さ」を示す一例として、興味深い事実が紹介されている。
いまでは多くの人々が海水浴などに興じる観光地、湘南海岸は、当時、本土で唯一本格的な上陸作戦訓練が行える演習場「茅ヶ崎ビーチ」として、米海兵隊・陸軍が盛んに利用していたというのだ。
サザン・オールスターズの曲にも出てくる「烏帽子岩」は、米陸軍の砲弾射撃訓練の標的となったことで崩落し、姿を変えたものだったということに、多くが驚くことだろう。
やがてこうした「身近な米軍」を好ましく思わない市民が声をあげはじめた。日本が独立を回復してもなお米軍が居座り続け、在日米軍基地は存続している。訓練という名のもとに近隣では砲弾が飛び、時には市民から死傷者も出ていた。また売春が横行し、風紀が乱れたという訴えもあったという(同書24〜27ページ)。
終戦直後の混乱期における反基地運動の基底には、「生活権を侵すな」という訴えがあった。さらに、自分たちの地域、ひいては日本という「国」に武器を持って立ち入ってくるのは、他国の、戦勝国の軍隊だという事実も、ある種の嫌悪感を引き起こす要因となっていた。
忌み嫌われる米軍基地は、やがて遠く南方の島に寄せられることになった。本土から、当時まだアメリカの統治下にあった沖縄への海兵隊の大移動は、駐留から4年後の1957年(昭和32年)から行われた。在日米軍基地の約75%(基地面積)が、日本の国土の0.6%しかない沖縄に集中している現状の礎は、こうしてつくられていった。
本土各地で激化した反基地運動。これが日米両政府における「基地問題を本土から消し去る」という方針を後押ししたと見ることができる。
「平和運動」としての反基地運動へ
1950年代の反基地運動が「生活権の擁護」に軸足を置いていたとしたら、1960年代以降のそれは、高度経済成長を遂げ豊かになりつつあった社会での「平和運動」的な性格を持っていた。
「もはや『戦後』ではない」と経済白書に謳われたのは1956年(昭和31年)、日本の国連加盟が認められたのもこの年だ。1964年(昭和39年)には東京オリンピックが開かれ、国土復興を世界に向けて大々的にアピールした。人々の生活は豊かになり、「三種の神器」が家庭に普及し、1968年(昭和43年)には国民総生産(GNP)が、当時の西ドイツを抜き世界第2位に。1970年(昭和45年)の大阪万博では来るべき輝かしい未来に国中が熱狂した。
一方で同盟国であるアメリカは ━━ 広島と長崎に原爆を落とした国は ━━ 太平洋のビキニ環礁で水爆実験を行い、大量の死の灰をあびた「第五福竜丸」は「第三の被爆地」と化した(1954年)。さらに1960年代に入るとアジアの一角、ベトナムでは激しい戦いを繰り広げ、その壮絶な戦闘の模様は日本を含め各国に伝えられた。
日本が稀に見るスピードで平和のうちに豊かさを手に入れ、そして在日米軍基地の多くは本土から沖縄に可能な限り集約されてもなお、基地反対の声が止まなかったのには、こうした冷戦化での「覇権国家アメリカ」の軍事行動に対する「嫌悪」のようなものがあったと見ることができる。反基地の波は反米感情と共鳴し、多分に政治的な、左翼的な運動として息づくことになった。
実際、砂川闘争においても、町ぐるみの基地拡張反対闘争から平和運動へと様相が変わっていったという。1956年(昭和31年)、ビキニ水爆実験を契機に盛り上がった核兵器廃絶運動「原水爆禁止世界大会」の第2回大会には、砂川の反対同盟から2名の代表が参加した。またベトナム戦争反対運動とも連帯し、ベトナムから法律家を迎えるなどの活動も行われた(『軍隊と住民』榎本信行著 71、84ページ)。
基地問題における、国家と国民との「共犯関係」
多くの人間から、基地問題や国家安全保障の不都合な真実を見えなくする「死角」と「構造」。東京に住む私たちは、いつしかその死角に生きることに慣れ、死角に隠れる様々な事象は「なきもの」として扱うようになったのではないか ── 「死角と構造」から基地問題を考えるという本テーマの根底にある、個人的な疑問である。
日米安保体制に波風を立てないよう、「基地問題を本土から消し去る」ことで足並みを揃えた日米両政府。その国家が嫌った波風を立てるのは、紛れもない国民であり、その総意とされる民意だ。
本土や「巨大なサークル」に囲まれた非・基地エリアに住む私たちと、1972年(昭和47年)にようやくアメリカから日本に返還された、基地だらけの沖縄のひとたちも、同じ日本の国民である。
我々が普段気にかけることなく生きているこの国の大きな「死角」と巨大な「構造」には、沖縄も横田も、普天間も辺野古も、そして首都・東京に住む私たちも、実は包含されている。
それは沖縄だけの問題ではなく、また横田や、その他基地周辺の市民だけのものでもない。基地問題はある種の「共犯関係」の上に成り立っている。
本土・首都圏で基地問題は死角化されたかもしれないが、しかし、基地の恩恵を誰が受けているのか、誰がそのコスト(金銭のみならず様々な手間、苦痛を含め)を払っているのか、そうした「つながり」すらも死角に追いやってしまうことが、一番憂慮すべき事態なのだと思う。
「沖縄の基地問題」という表現は、「沖縄にこそ問題がある」と読めてしまう。
本土にいる私たちは「問題は局所的なものである」という認識を持ってしまいがちだ。同じ日本という国にいながら、意識の関連性が断たれ、他人事として受け止めてしまう。
物理的に見えないという文字通りの「死角」よりも、この「意識の死角」の方が、切実なように思えてならない。■ bg
(第2章 終わり)