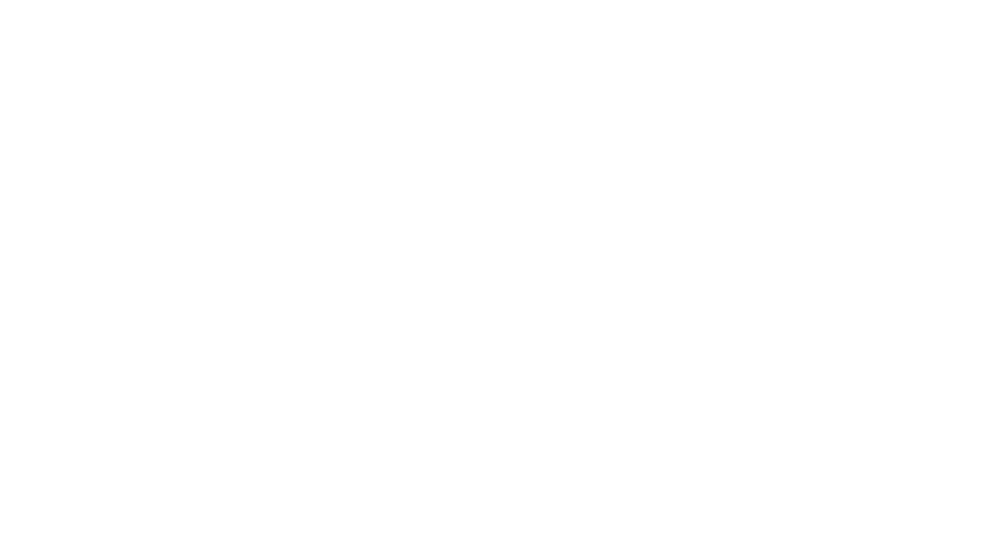「アーロンチェア」の上で考えた、椅子という家具について

二十世紀は「椅子の時代」だった
「何故、世界中のデザイナーはこぞって椅子をデザインするのでしょうか?」
編集者をやっていた頃に取材したとある有名なデザイナーの方に、素朴に過ぎる質問を投げかけてみたことがある。自身もユニークな形態の椅子を世に出していた彼は、「これまで多くのデザイナーが取り組んできたから、そこに自分も挑戦してみようと思えるのではないか」といった主旨の答えをくれた。少なくとも彼を椅子の創作へと駆り立てるものは、そこにあるようだった。
美術関連の著書が多い評論家の海野弘も、600ページ近くにもなる大著『モダン・デザイン全史』(美術出版社)のなかで「椅子の二十世紀」という章を立て、こう記している。
家具の中で、椅子ぐらい親しまれ、それだけに変化に富んだデザインを持つものはないだろう。特に現代のデザイナーは椅子をデザインするのが好きだ。二十世紀に入って、椅子のデザインは多様になる。二十世紀はもしかしたら、椅子の時代といえるかもしれない。(382ページ)
そう、デザイナーは椅子をデザインすることが好きなのだ。そしてそんなデザイナーたちが様々な椅子を出したことで、二十世紀は「椅子の時代」になった。
果たしてデザイナーを惹きつける椅子の魅力とは何なのか。海野前掲書の以下の一節から、そのヒントを見つけてみる。
直立し、二本足で歩行する動物となった人間は、首、肩、背中、腰、足などにかなり無理な負担を受けるようになった。したがって長時間立っていられないので、時々、腰掛けて休まなければならない。しかし腰掛けの姿勢もまた安定したものではない。<中略>つまり人間は椅子の上でも安定せず、ぐらぐらしているのだ。したがって、究極の椅子を見つけるのは困難である。(385ページ)
また、デザインエンジニアで東京大学生産技術研究所教授の山中俊治は、著書『デザインの小骨話』(日経BP社)のなかで、人間の姿勢についてこんなことを書いている。
バランスをとることで、筋肉の負担が少なくなる姿勢を「立つ」という。ほとんどの筋肉を弛緩させる姿勢を「寝る」という。ある筋肉を弛緩させ、残りの筋肉がバランスをとる姿勢を「座る」という。生物の「楽な」姿勢は均衡と弛緩で成り立っている。(16ページ)
アートが「個の発露」なら、デザインは「摂理の発見」である。
人間という不安定な生き物と密着し、身体を支える椅子づくりには、その使われ方やユーザーの体型、好みなど数多の要素を相手取ることが必要とされる。同時にデザイナーには、造形を含めた新たな価値も求められる。冒頭のデザイナー氏の「挑戦」とは、“究極の椅子”をつくりあげるという困難性へのチャレンジにほかならないのである。
新しい技術、新しい素材の誕生
二十世紀に花開いた椅子の時代。その背景には、それまでなかった素材や技法が次々と発明され、次々と新たな形状や構造が可能になっていったという、技術的な進歩があったことは言うまでもないだろう。
例えば、ごくありふれた木材であってもそうだ。木の棒と板を格子状に組んだシンプルなものから、アルヴァ・アアルトが「パイミオチェア」(1931年頃)で用いたように、スライスした木を重ねプレスし、曲げて整形する技術が確立されると、身体と接触する座面や背もたれに滑らかな曲線の面ができるようになった。
より加工が容易な金属なら、マルセル・ブロイヤーによる「B3チェア」(1925年)。自転車から着想を得たというこの椅子は、工業製品として精度の高いスチールパイプが製造できなければ実現不能という意味で、産業の高度化の賜物である。そして、フォルムを自在にできるプラスティックが普及すれば、世界初のシングルピース・プラスティック・チェアたる「スタッキングチェア」(1960年)をはじめとするユニークなカタチの椅子たちが誕生することになる。
自転車や自動車、飛行機などといった様々なプロダクトから新たな素材や技術が生まれ、大量生産の道筋ができていく。まさに二十世紀の潮流の一部を、椅子が担ったと言えるだろう。
そんな二十世紀の末に産声をあげたのが、ハーマンミラー社の「アーロンチェア」だった。
オフィス環境を一変させた「ハーマンミラー」
1905年にアメリカはミシガン州ジーランドで設立された「スター・ファニチャー・カンパニー」をそのオリジンとする「ハーマンミラー」社。当初は家庭用家具を手がけていたこの企業は、1960年代に転換期を迎えることになる。デザイナーであり教師、さらに彫刻家と多才な人物だったロバート・プロプストがリサーチ部門のトップに就くと、同社はオフィス環境の改善に取り組むことになった。
「現代のオフィスは荒廃している。活気を奪い、才能を妨害し、成果を上げない。意図したとおりに実現されず、取り組みが失敗に終わることが日常茶飯事である」
こうしたプロプストの問題意識から生まれたのが、「アクションオフィス」なる概念とそのプロダクト群だった。それまでの職場といえば、オープンスペースにデスクが規則正しく並べられただけの空間であり、人々は他人の会話や雑音など騒然としたなかで業務にあたらなければならなかった。これを解決すべく考え出されたのが、いわゆる「キュービクル」と呼ばれる、パーテーションで各人のスペースが区切られた半個室的なオフィスだった。
プロプストは、デザイナーのジョージ・ネルソンと協働し、「アクションオフィスI」(1964年)、そして「アクションオフィスII」(1968年)を発表。パネルで仕切られた空間に、車輪が付いたチェアやデスクなどオフィスに必要な什器をモジュールとして用意することで、多様なニーズに応えられるという画期的なこのシステムは、アメリカのオフィスの景色を一変する契機となった。(以上、ハーマンミラー公式サイト:ロバート・プロプスト より)
「アーロンチェア」は“椅子の時代の総決算”
オフィスファニチャーの地平を切り拓いてきたハーマンミラーが「アーロンチェア」を発表したのは1994年のこと。椅子の時代の総決算ともいうべきものであり、同社を代表するプロダクトとして現在もなお君臨しているのには、ちょっとした歴史の“いたずら”があったようである。
1990年代後半、世は“インターネット・バブル”に浮かれ、新興ドットコム企業はみなオフィスに高価なアーロンチェアを並べては、従業員は誇らしげにそこに座った。当時飛ぶ鳥を落とす勢いだったこうしたインターネット企業は、ある種の成功の証、いわば「王座」としてアーロンチェアに泡沫の夢を重ねたのだろう。まさに椅子の時代である二十世紀を締めくくるにふさわしい現象だった。
バブルの象徴のようなアーロンチェアだが、実際、そのモダンかつエルゴノミクスなデザインは、座るものに時代の先端を行くかのような気分をもたらすとともに、椅子に求められる要素も高次に盛り込まれている。いろんな体格に合わせるべくサイズを3種類用意し、それぞれに上下前後、腰回りのサポートの調整機構を備え、絶妙のフィット感を約束する。特徴的な「ペリクル」と呼ばれる張地が座面や背もたれの圧を適度にいなし、ちゃんと設定すれば長時間座っていても苦にならない。
我が家にアーロンチェアがやってきたのは2004年のこと。10万円をゆうに超える高い買い物ではあったものの、長く座ることが宿命となる現代人としては椅子に妥協はしたくなかった。あれから16年が過ぎ、コロナ禍の在宅勤務でこれだけ重宝されるとは夢にも思っていなかったが、いまもなお尻と背中を付き合わせる良き相棒として、壮年を迎えた私を支えてくれている。■bg
things to buy



reference
ハーマンミラー「アーロンチェア」 https://www.hermanmiller.com/ja_jp/products/seating/office-chairs/aeron-chairs/