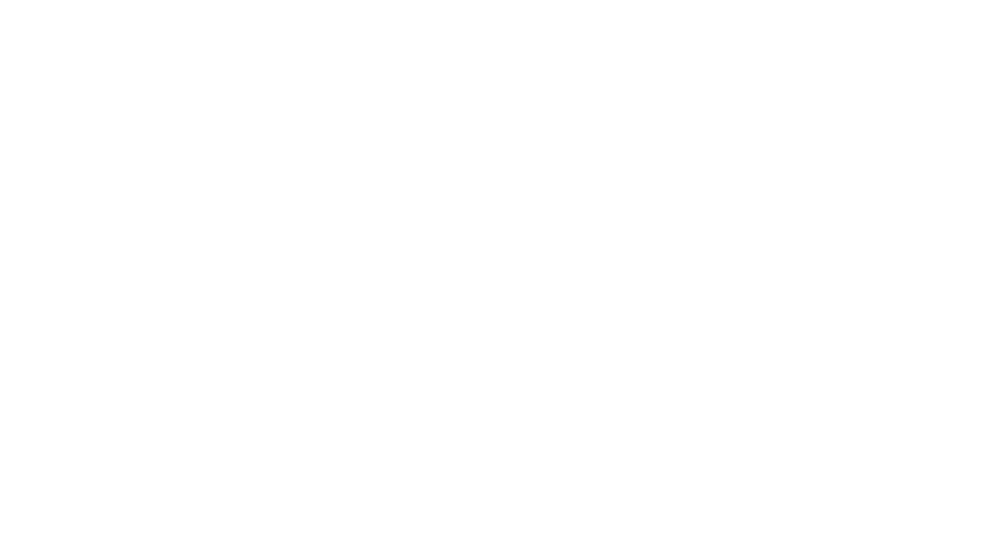『福島の美術館で何が起こっていたのか』を読んで
震災・原発事故を語る、福島に住む人たちの等身大の言葉
『福島の美術館で何が起こっていたのか ── 震災、原発事故、ベン・シャーンのこと ──』という本の存在は、2012年の秋頃にツイッターのTLで知った。
「編集グループ〈SURE〉」という京都をベースに活動するグループから出ている。このSUREは、一部書籍を除き取り次ぎを通さないという方針の、とてもユニークな集団であり、今回も郵便振込で直接購入した(出版不況の折、本好きとしてはこういう独自の取り組みを素直に応援したい)。

作家・黒川創とSUREのスタッフらが、巡回展「ベン・シャーン クロスメディア・アーティスト」が開かれていた福島県立美術館を訪れ、学芸員(元学芸員を含む)の方々から座談会形式で話を聞いたものを中心とした一冊である。
時期は東日本大震災から1年4ヶ月経った2012年7月。被災のこと、原発事故由来の放射性物質で汚染された地域に住んでいることなどが、赤裸々に綴られているのだが、そこからはメディアが盛んに取り上げる「大震災」「大津波」「原発事故」といった、非日常に過ぎたストーリーといった感じは受けない。
ごくありふれた生活のなかで震災に遭い、危険な状態にあるかもしれない(当時は情報が極端に少なかった)原発を視野に入れながら、ある人は福島から会津若松の実家に逃げ、ある人は当時の勤務地だったいわきで津波の被害を間近に感じ、またある人は降ってきた雪が肌にあたり「ぴりぴり」と感じ、また屋内退避のサイレンに戦々恐々とし……ということが、等身大の言葉で語られている。
恐ろしい力で津波に飲み込まれた。
いつ原子炉が暴走しだすか分からないなかで原発作業員による懸命な作業が続けられた。
様々なメディアが伝えるそれらの情報は厳然たる事実なのだが、そういった堪え難い、悲しい出来事や極限下の体験談は、テレビから流れる膨大な映像から状況を推し量ろうとしても限度があった。自らの想像力の範疇を超えてしまっていた。
それに比べると、福島市に暮らす学芸員の方々の声にはある種の“近さ”を感じることができる。どちらがいい悪い、軽い重いということではない。受け取る方の感度の問題である。
東京に住んでいると、福島出身者と出会うことはあっても、実際に現在も住んでいる人と会話することは稀である。本書から聞こえてくる、福島に暮らす人たちの生の声は、いま彼ら彼女らがどのように暮らし、何を思っているかを知る、とても貴重な手がかりとなった。
そして、程度の差こそあれ、やはり放射能汚染を被った地域で生活を続ける自分たちに、また311以後の世界を生きていく人たちに、何かしらの示唆を与える内容であったと思う。
逃げたか、逃げなかったか
座談会に出ていた学芸員6人と編集スタッフのなかで、とても印象に残った人物が2人いる。
ひとりは現職の学芸員で、小中学生のお子さんを持つお母さんでもある増渕さんという方。震災後も、家族とともに福島で暮らしている。
もうひとりは、聞き手として会に参加した中尾ハジメ京都精華大学教授だった。スリーマイル島原発事故で被災地の調査を行った人物であり、今回も原発問題を追う人間の視点から第三者的に話に加わっている。
福島に住む人々の、日常のリアリティ(の一端)と、県外からやってきた人からの原発という社会的問題提起の交錯。2人の発言には、くっきりとしたコントラストがあらわれていた。
増渕さんは、震災直後、原発に未曾有の危機が迫っていた頃に、別の学芸員から福島脱出に誘われながらも、逃げない決断を下したという。
私、子どもがまだ小さいですし、気持ちも動いたんですけど、いろんな人の話を聞いて。主人の家族はみんな福島に住んでいますから、うちだけが出るわけにいきません。それで、最後に堀(筆者注:美術館の同僚で座談会にも出席)に電話したんです。「堀さん、どうします?逃げますか?」って聞いたら、「逃げないです」って。
(125ページ)
とどまる決断の背景には、エンジニアであるご主人の理系ならではの状況判断というものもあったというが、福島から逃げないと決めるまでにはきっと葛藤があったはず。逃げたい気持ちと、逃げられない(逃げづらい)という理由…… 最後の電話で、逃げない決心へ背中を押してもらったのではないだろうか。
この時の彼女の状況に、もし自分が福島に住んでいたら、という仮定を重ね合わせる。自分は逃げていたのだろうか、それともとどまっただろうか。
原発が爆発するシーンをテレビでみて、東京に住んでいる私の友人も一時的に西日本に家族を退避させたりしていた。我が家とて例外ではなく、福島はいわきの義理の母たち11人+犬2匹を、都下にある我が狭小住宅に迎え入れるという非常事態に陥っていた。“避難民”と化した義理の家族を受け入れたことで、そもそも東日本脱出などは想像もつかなかったのだが、仮に自分たち家族だけだったとしても、東京からは「逃げなかった」のではないかと思う。
そもそも、逃げるような場所がすぐに思い当たらない。妻の実家はいわき、私の両親は隣に住み、親戚は関東近県で、友人もしかりだ。そして何より、ここに私の家があり、家族がいて、生活がある。自分はいいとして、逃げる場合に家族をどうやって説得するのか。仕事はどうするのか。かかるコストの見込みはあるのか。
火事場にいればバカヂカラも出ればすぐにでも逃げ出すだろう。しかし目にみえぬ放射能から逃れるのは簡単ではない。そもそも放射能がやってくるという経験をしたことのない事態ではなおさらだ。「放射能からの逃避」に確たる説得力を込めるには、私は少々無知過ぎたし、また生活にまつわるあらゆるものが一カ所に集まり過ぎていた。
── という言葉を並べてみると、かなり言い訳じみていることに気がついた。
そう、私は(福島ではなく東京だったが)自らの原発事故への初動には多少なりとも後悔の念がある。そして住み慣れた東京で暮らし続けることに、僅かながらも、しかし心のある所定の場所において、淡い不安をおぼえている。そういう人は、少なくないんじゃないだろうか。
福島で暮らしているなかで、一番つらいこと
話を本書に戻す。
放射線量が高いとされる福島に住み続ける増渕さんたち。彼女の言葉は、楽観的でもなければ悲観的でもない。ただ、迷いのなかでどうやって生きていくかという、少しずつでも前に進もうという気持ちが感じ取れる。
しかし、前進しようとする彼女の気持ちを萎えさせるような出来事もある。
放射線量ではない。
生身の、見ず知らずの、県外に住む人たちの声だった。
放射線自体は、恐いながらも気をつけて生活してきて、去年の九月から一二月にかけて、子どもにガラスバッジをつけて線量を測ったんです。結果としては、かなり低かったんです。
<中略>
安心材料というほどではないですが、暮らしていく上で、判断基準になるデータがそこで一つ。そして、今年の春に内部被曝の検査が始まって、それも、うちの子どもについては不検出だったんです。
そのデータをどうとらえるかは、人によって違うかもしれないけど、客観的データであることは確かで、そういうのがだんだん積み上がってくるなかで、平常を取り戻しつつあるのかなと思います。
一番つらかったのは、県外の方などに、ガラスバッジをつけて子どもたちを生活させていること自体がおかしいといわれることですね。
(156~157ページ)
 彼女は美術館の情報を発信する目的で、福島県立美術館の学芸員という肩書き付きで実名でツイッターをはじめたという。
彼女は美術館の情報を発信する目的で、福島県立美術館の学芸員という肩書き付きで実名でツイッターをはじめたという。
美術館の情報を届けるはずが、放射能の話しか入ってこなくなることに困り、知らない人にいかに福島は危険かということを諭され、たまりかねて福島に住んでいる人もいるんだから言葉を選んでほしいといえば非難され、ついにはツイッターをやめた。
フォロワーは県内の子供を持つ親ではなく、東京や関西の、放射能に強い関心を持つ人たちだったという。
福島=放射能。
好むと好まざるとにかかわらず、この図式が定着してしまったいま、その色眼鏡は実際にそこで生活を続ける人たちをみえなくしてしまうこともある。彼女は、特に県外で原発に反対している人たちに向けて、「想像力を持ってほしい」と訴えている。
原発は再稼働すべきではない。
福島をみてみろ。人が住めない危険な場所になってしまったじゃないか。
という声が、その「人が住めない危険な場所」にいまも住んでいる人たちに届き、その人たちを苦しめている。そこで暮らす人たちも、必死に放射能を勉強し、対策をとろうとしている。親ともなれば、子供たちの健康にどれだけ配慮をしているか、それこそ想像に難くない。
原発事故、その後の放射線量との目にみえぬ格闘、そして外部からの非難の声や好奇の目。それらすべてをひっくるめて「原発被害」だと増渕さんはいう。
「幸せ」と「原発」の間
さて、印象に残ったもうひとりの中尾さんは、増渕さんと対極をなしている。
中尾さんは、増渕さんの「想像力を持って」という訴えには、(放射能は)危険なんだという問題提起自体に問題はない。東京や関西のような県外の、状況をよく理解していない人が福島に住む人たちを批判すること自体が変なのである、と返す。実際に現地で暮らしている人たちの日常や置かれている状況をみないでは、何も分からないではないかと。実際、彼自身スリーマイル島に赴き、そして福島にも足を運んでいる。
その上で、原発や核がもたらす問題に切れ込む。
しかし、そうやって、今まで繰りかえし、彼らは放射線被害、放射能汚染事故の過小評価をずっと続けてきた。広島でも、まだそれを続けているんです。これからも数字でしか喋らない人たちが、権力を持ち続けるでしょう。その中で嫌な目にあっている人たちは、どっちの話を聞いても、嫌な感じしか残らないわけです。本当に嫌なことだけど。
<中略>
でも結局は、すべて何がなんだかわからないことになってしまって、公式的には、たいしたことはなかったということになってしまう。それが本当に嫌だから、いろいろ、ぼくはこんなことに首をつっこむんだけれども、それで誰かが幸福になるかといったら、ならないです。
(170~171ページ)
上記の最後「幸福」のくだりは、増渕さんの問いに対応している。福島にいる人たちがどうやったら幸せになれるのか。学芸員として、親として、増渕さんの関心は「福島で幸せに生きる」ことに向かう。一方で中尾さんの視線は、あくまで原発問題に注がれる。
「幸せ」と「原発」の間には、何がみえるのだろうか。
「二項対立」だけでは原発を巡る諸問題は一向に解決しない
この『福島の美術館で何が起こっていたのか』の個人的な一番の読みどころは、増渕さんと中尾さんの対話だった。
原発を忌み嫌う立場を同じにしながら、両者の話はなかなか噛み合わない。2人が語る事象が、同じ原発でありながら、同一のレイヤー(層)の上にはないからだ。
原発問題は複雑だ。ひとたび事故が起こればまったく関係ない人を含めて被曝にさらされ、国土が失われ、故郷は奪われ、また平時であっても労働者を高い放射線と事故の危険にさらす。被曝と生命への影響というサイエンスの領域から、エネルギー政策や核武装という国家規模の思惑、原発ムラと呼ばれる複合利権構造、過疎地域にカネをばらまき治めるという原子力政策 ──それぞれにそれぞれの当事者が絡み、様々な層を形成する。
その幾重にも重なる層を一気通貫に串刺しにして議論することは、本来なら困難を極める。少なくとも、ついこの間まで原発問題が社会のごく一部でしか議論されてこなかったこの国においてはなおさらであろう。本書の2人の間にある齟齬は、原発被害に遭いながら必死に生きていくという局面と、社会として原発がもたらす諸問題とどう向き合うかという、異なるレイヤーの捻れだと思う。
では福島原発事故が起きてしまったいま、私たちはこの問題にどう取り組めばいいのか。いいアイディアを提案することは正直私の手にあまるのだが、ひとつだけいえることは、「二項対立」だけでは原発を巡る諸問題は一向に解決しない、ということに、そろそろ多くの人が気がついた方がいいのではないか、ということだ。
原発を「是」とするのか「非」とするのか。その表層的な、議論というよりは罵り合いに近い不毛なやり取りがあれから2年も続いている。そのなかに「福島」が都合よく内包され、「悲劇の地」として聖地化されているのではないか。
非とする側には、「放射能に苦しむ福島に住む人たちを憂える」という気持ちがあるかもしれないが、個人の心情として持つのは自由だが、それを実際に福島の人たちにぶつけるのは、言ってみれば、大きなお世話である。
さらに実情をみもせずに福島が危険だというレッテルを貼ることは、反原発を唱える人たちの信ずる「原発=悪=福島をみろ」という勝手な公式を成り立たせるために、福島の人たちを利用しているに過ぎないのではないかとさえ思うこともある。
増渕さんの言葉の節々からは、いやこの本に出てくる他の学芸員を含めて、混乱や不安や希望の濃淡のなかで日々の生活を必死に営んでいることが伝わってくる。
原発は是か非か。汚染された地域は安全か危険か。本当は、白と黒の間には多様なグラデーションが横たわり、ひとつの事象、ひとりの人間とて、その明暗や色調の違いの波を行ったり来たりしている。
複雑なものを単純にみようとすればするほど、色や明るさの微細な違いを拾い切れない。人間の生活の多様な営みと豊かさを知らずして、どこに復興や、前進の道が拓けようか。
「あの日」から2年が経過した。様々なことが伝えられ、叫ばれているが、「正しいこと」として信じ切ってしまうとみえないものもあるということが、この本の行間に綴られていると思う。
世界と丁寧に接することでしか、解決の糸口はみつけられない。そのための一助として紹介したい一冊である。■ bg
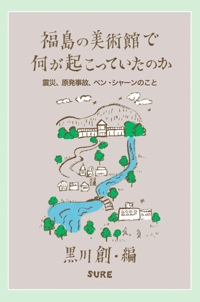
『福島の美術館で何が起こっていたのか
── 震災、原発事故、ベン・シャーンのこと──』
黒川創 編
発行・発売 編集グループSURE
定価2415円(本体2300円+税)