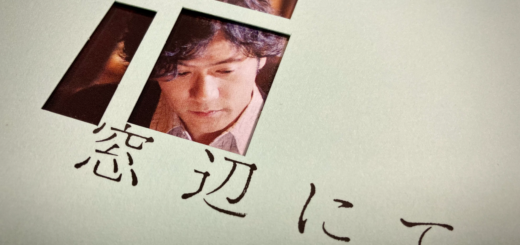「いつでも、誰の前にも、道はひらかれている」の意味〜ドラマ『アフリカの夜』〜

若い頃に観たドラマのなかで、1999年にフジテレビでオンエアされた『アフリカの夜』は、ずっと心に引っかかっていた。そのいちばんの理由は、「いつでも、誰の前にも、道はひらかれている」という、希望に満ちた象徴的なセリフにあった。「道はひらかれている」が意味するところは何だったのだろうか。自分なりの答えを、四半世紀以上たって探してみた。
「メゾン・アフリカ」の住人たちが織りなす群像劇
本作は、「メゾン・アフリカ」という風変わりなアパートの住人たちが織りなす群像劇だ。結婚式の日に婚約者が逮捕され、好奇の目にさらされることになった杉立八重子(鈴木京香)がアパートに引っ越してくるところからストーリーは始まる。
アパートに住むのは、8年前に八重子にプロポーズするも別れた過去を持つ木村礼太郎(佐藤浩市)、礼太郎のいまの彼女である女優の卵の相沢有香(松雪泰子)、さらに礼太郎の妹でブラコン全開無敵キャラの緑(ともさかりえ)、そして惣菜屋「おかずの丸ちゃん」のおかみさん丸山みづほ(室井滋)。個性豊かな面々による自由奔放なアパートの雰囲気に最初は慣れなかった杉立もやがて打ち解け、周囲からの信頼と内なる自信を獲得していく。
そんな折、”丸ちゃんのおかん”こと丸山みづほが、夫殺しの指名手配犯ではないかという疑惑が持ち上がる。時効間近とマスコミが騒ぎ立て、警察の執拗な捜査が続けられるなか、アフリカの住人の間でもいよいよグレーが黒に変わっていくと、八重子はみづほこと本名「亀田伸枝」に自首を促す。普段は明るいみづほは、やっとここまで逃げてこれたのだ、捕まるわけにはいかないと鬼の形相に変わり、2人の間に緊張が走る。
DV夫から逃れるために殺人を犯し、家族から「捕まるようなら死ね」と罵声を浴びせられながら、優しい内縁の夫・良吉(國村隼)と慎ましくも幸せな生活を送っていたみづほ。徐々に迫り来る警察、ジリジリと近づく時効の瞬間に向かって物語は加速度を増していく。
「不退転の覚悟で生きろ!」
スキャンダルに巻き込まれた八重子は、傷心を引きずりビクビクした生活を送っていたが、そんな彼女に「自信を持っていけ」と背中を押したのは他ならぬみづほだった。八重子のみならず、女優業や礼太郎との恋愛に戸惑いを見せていた有香も、みづほに元気づけられたことで強さを手に入れていった。
だがみづほの励ましは、DV夫から逃れようと殺人まで犯した、自身の経験からくるものだった。
警察に追われていると感じたみづほは、逃亡の途中で偶然すれ違った、オーディションに行く前の有香に勢いよくこう言い放つ。
「一度しかない人生、幸せになれ!諦めるな!後ろを振り向くな!不退転の覚悟で生きろ!」
力強いこの言葉も、暴力夫から、警察から、自分の暗い過去から、絶対に逃げてやるという、みづほの強い信念からのものだった。
みづほは、過去から逃げようとした。しかし八重子は、逃げないで自首してほしいと願った。恩人であるみづほに、なぜ八重子はそう言ったのか。八重子のこの心境に影響を与えたのが、礼太郎との関係だった。
8年前のプロポーズのこと
8年前、土砂降りのなか壊れた車を一緒に押していた八重子に「結婚しよう」とプロポーズした礼太郎は、当時をこう振り返る。
「住宅展示場のこぎれいなモデルルーム、つるつるした表紙の新生活のカタログ、あの頃きみが求めていたものは、結局それだった。土砂降りの雨のなかで車を押しながらのプロポーズ、明日が見えない男との暮らし、そういったものはきみのカタログには載っていなかった」
八重子を小馬鹿にしているようだが、自分自身も未熟だったと認めている。
「あの時、俺の人生も夜だったし雨だった。一本映画を撮って、わけの分からないやつにもてはやされ、自分もその気になって次の映画を準備してて、結局撮れなかった」
礼太郎の撮った最初にして最後の映画のタイトルが『アフリカの夜』。映画の夢を諦め、その後に経営コンサルタントとしての道を歩んだ彼は、もしあの時、結婚していたら、2人の関係は失敗に終わっただろうと八重子に話す。
2人は、過去の自分たちと向き合うことで、8年後の再会とこれからを考えようとした。
八重子は、過去の自分を受け入れることで、突破口を開いていくのである。
幸せへの「道の選択」
話をみづほと八重子に戻すと、傷を負った2人の女性の、選ぼうとする道の違いが示される。
逃げようとするものと、逃げるのをよしとしないもの。
八重子が求めたのは、自首というひとを殺めた罪を償うということ以上に、みづほ自身に「自分の道を歩いてほしかった」のではないだろうか。
いつまでも過去に縛られ続けてはダメなんだ。負の力で進み続けても、決して幸せにはなれないんだ。清濁を併せ呑み、自分を受け止めてから全ては再スタートするんだ。みづほが教えてくれたことは、そういうことだったんじゃないかと。
ドラマの佳境、自首を促していた八重子が心変わりをする。故郷の港町で、有香を振り切って逃げようとするみづほは、有香が海に落ちると足を止め、溺れる有香を助けに戻る。そのうちに迫り来るパトカーのサイレン。いよいよ警察に囲まれた絶体絶命のみづほに、「逃げて」と言ったのは八重子だった。殺人犯の亀田、隣人であり恩人であったみづほへの複雑な思いが垣間見える、とても人間的なシーンだった。
礼太郎は、なぜ死ななければならなかったか
みづほの逮捕後に起きたのが、礼太郎の死だった。
逮捕のニュースを聞いた礼太郎は自暴自棄となり、チンピラに絡まれて腹を刺され絶命する。日本のドラマにありがちな、1クール内での忙しない展開に少々面食らったものだが、あらためてこの物語における礼太郎の存在を考えてみると、「道はひらかれている」という重要な言葉を残しながら、彼は脇役であったことに気がつくだろう。
礼太郎は、「道は開かれている」というメッセージを示すことはしたが、その道を進もうとする力は、八重子や有香、みづほ、そして緑といった女性たちの方がまさっていた。
彼は映画を撮るということを諦め、そんな自分を持て余しながら生きていた。ロマンティストかつ冷静に物事を見る目を持ち合わせていたものの、すっかり道を外れてしまっていた。突破する力がなかった。いわば夜の闇のなかにいたのである。
みづほが捕まり、メゾン・アフリカの住人が愛した商店街が、地上げ屋チンピラに壊されていく。夢を諦め、それでもみづほやアパートや商店街に支えられてきた彼は、いよいよ生きる場を失い絶望的になった。本当は誰よりも多い熱量を持っていたのに、それを振り向ける道を見失ってしまっていたのが、礼太郎の不幸だったのではないか。彼の死は、必然というよりも象徴として描かれていたように思う。
女性たちの「ゆるやかな連帯」
『アフリカの夜』は、実際のところ、女性による女性のためのドラマだったと言えるのかもしれない。
テレビドラマを研究している早稲田大学文学学術院教授の岡室美奈子は、著書『テレビドラマは時代を映す』で、本作についてこう記している。
最終的にみづほに「逃げて」と言う八重子の言葉にもぐっときたが、宮本理江子(当時は石坂理江子)による逮捕シーンの演出も秀逸だった。みづほは、殺人を犯して整形手術を繰り返しながら時効直前まで逃亡した福田和子をモデルにしているが、みづほの夫殺しの背景には夫の家庭内暴力があった。殺人は許されざる犯罪である。しかし男性ばかりの警察官に囲まれ、必死に抗いながらも取り押さえられてしまう女たちの姿がスローモーションの映像と音楽のみで描かれ、不思議な感動を喚び起こした。女性たちは無力だが、決して組み伏せられるだけの存在ではなく、連帯することで大きな力に立ち向かうことができるのだと、このドラマは教えてくれたのだと思う。何度も繰り返されるセリフのとおり「道は開かれている」のだと。
岡室美奈子著『テレビドラマは時代を映す』早川書房(2024年)
岡室は、『アフリカの夜』をはじめ『29歳のクリスマス』(1994年)、『きらきらひかる』(1998年)と、1990年代のテレビドラマには女性のゆるやかな連帯を描いた作品があったと指摘する。そしてそれら作品がいまもなお評価される背景には、女性を取り巻く生きづらさが解消されていないことがあるのだとも。
『アフリカの夜』では、有香が礼太郎の子供を宿し、ひとりで産む決心をするのだが、『29歳のクリスマス』でも同様のシナリオが織り込まれている。実社会において、女性の地位やシングルマザーといった問題はいまもって解決されたわけではないことを考えると、なるほどと納得してしまうのである。
そう考えれば、礼太郎の死も、八重子らに女性同士の連帯をもたらすための設定と見ることもできるだろう。
「道はひらかれている」の意味とは
「いつでも、誰の前にも、道はひらかれている」という印象的なセリフを読み解いてみると、こういうことになるのではないだろうか。
本作を通して浮かび上がるのは、
- 「逃げる」と「前に進む」は、同じようで違う。
- 過去を含め自らと正対しない限り、前には進めないし、幸せにはなれない。
- 進もうとする「道」は、自ら選べる。
たとえ暗い夜が続いていても、あなたがその気にさえなれば、幸せになれるんだということなのではないか。
最終回、取り調べを受けていたみづほはこれまでを振り返り、「つらいことばかりだった」とこぼしながら、「最後にアフリカで過ごした日々は幸せでした。これでよかったんですよ」と穏やかに語っていた。
「いつでも、誰の前にも、道はひらかれている」。時代を問わず、また本質的に男女の違いに関係なく届く、生きる上で大事な指標となるような前向きなメッセージだとあらためて思った。■bg
reference
- FOD 『アフリカの夜』 https://fod.fujitv.co.jp/title/4437/
- 岡室美奈子著『テレビドラマは時代を映す』早川書房(2024年) https://amzn.to/4a4d40m